「若い人材を育て、研究の発展に貢献」赤沢学先生(明治薬科大学)

ご経歴を教えてください。
外資系の製薬会社で、医薬品の臨床開発を10年ほど担当していました。当時はICH-GCP(International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use-Good Clinical Practice:医薬品規制調和国際会議で決められた医薬品の臨床試験の実施に関する基準)が新たに導入された時期で、今後日本の治験がどうなっていくのだろうか? と少し不安に感じていました。
あるきっかけで、医薬品の費用と効果を調べる学問である薬剤経済学という分野を知り非常に興味を持ちましたが、日本ではこの分野を学べる教育の機会がありませんでした。そのため、アメリカに留学して薬剤経済学を勉強したいと思い、会社の海外留学制度とフルブライト奨学金の資金援助を幸いにも獲得して、1999年からイエール大学へ留学することになりました。
イエール大学では、薬剤経済学だけではなく、医療政策や医療マネージメントなど幅広く2年間勉強し、学位(Master of Public Health: MPH)を取得しました。卒業後は日本に帰ってきて、新薬の薬価交渉に関する仕事をしていました。海外の企業では薬剤経済学を専門に担当する部門があって、経済評価や薬価算定を行うのですが、日本ではそういう部署がまだありませんでした。これでは、せっかく2年間アメリカで勉強してきたことが活かせないと考え、アメリカにもう一度戻りました。
アメリカでは引き続き薬剤経済学を勉強されたのでしょうか?
そうですね。薬剤経済学と医療政策を引き続き勉強しました。アメリカでは大規模なデータベースを使って、医薬品の有効性や安全性、費用に関わるものを評価する研究が盛んになってきた頃だったので、その分野の研究で学位(PhD)をとりました。学位取得後はアメリカの政府機関のひとつである、アメリカ疾病管理予防センター(Centers for Disease Control and Prevention:CDC)で、医療経済学のフェロープログラムに参加したのですがプログラムの途中、家庭の事情で帰国することになってしまいました。帰国後は東京大学大学院薬学系研究科の津谷教授のもとで研究員として日本での研究活動を始めることになりました。
アメリカから帰国後、日本ではどのような研究をなさったのでしょうか?
アメリカでは各種医療保険会社のデータベースを使用して研究を行ってきましたが、日本ではこのような研究はあまり普及していませんでした。そこでまずは、健康保険組合のレセプトデーターベースを使って、高齢者に不適切な医薬品の使用実態調査に取り組みました。また、日本に帰ってきて驚いたのですが、アメリカと違い、日本では薬剤師の仕事が適切に評価されていませんでした。そこで、薬剤師に焦点をあてた研究を始めようと思い、東京大学の先生たちと一緒に始めたのがブラウンバッグ運動です。この運動は広島県の自治体と薬剤師会などの協力を得て、お薬の使用実態調査として実施しました。患者が使用している服用薬を薬局に持ち込んでもらい、適切に使われているか、もし問題があった場合どのように解決するか、といった研究を行いました。その後、他の地域の薬剤師会や保険薬局の先生方にも、この運動に参加していただいています。薬剤師の存在意義を明らかにするためにも、薬剤師が患者サービスを提供することで、患者にどのようなメリットがあるか評価して行くことが大切です。しかし、このような研究は介入研究を行うのは難しく、地域医療に携わる薬剤師と一緒に試行錯誤を重ねながら研究を行っています。これが、1つ目の研究です。
2つ目は、PMDA(医薬品医療機器総合機構:Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)がMIHARIプロジェクトとして実施しているような医薬品の安全性評価です。医療情報が電子化された大規模なデータベースができつつあるので、このデータベースを活用した薬剤疫学研究を進めています。
3つ目は、医薬品の経済評価です。新薬や医療機器の保険償還や価格設定に、費用対効果を判断基準に使えないかの検討が厚生労働省を中心に進められています。費用対効果評価を行うためのガイドライン整備、費用や効果のデータをどこから持ってきたほうがいいのかなど試行的検討を行っています。
アメリカでの留学経験をお持ちですが、英語でご苦労された経験はありますか?
留学する前から英語で苦労していて、留学に必要なTOFELの点数をあげる事にも苦労しました。基本的な英文法を一から勉強し直してやっとスコアがあがりました。最初のイエール大学留学で実感したことは、英語力の問題だけでなく、授業の中身を知らない、つまり知識不足でなかなか授業についていけないことでした。知らないことは聞き取れなかったり、理解できないというリスニング力で苦労しました。
2つ目は、ディスカッションです。大学院で行うグループワークでは、自分自身がどう貢献できるのかが重要視されていて、当時の自分にとっては負荷が大きかった。1年目は語学力の問題もあり、どのように貢献できるかわからず苦労しました。2年目に入り、医療政策学という授業の中で、医薬品のプライシングと保険制度についての議論がしたくて、グループリーダーとして立候補し、プロジェクトのまとめ役になりました。自分の興味のあるトピックを率先して行うことが非常に良い経験になり、語学力についても少し自信がつきました。
3つ目はライティングです。アメリカの大学院はエッセイを数多く書かされます。最初はどうやって書いていいか戸惑いました。大学院で英語の専門家をチューター(家庭教師)として雇っていて、その先生からプライベートレッスンのようなものを受けることができました。課題レポートを早めに書いて、それを提出前に全部チェックしてもらいました。最終的には修士論文まで見ていただいて、とても良いトレーニングになりました。1つ1つ色々な経験を通して、なんとなく身につけられたなというのが最初の留学での経験です。
研究者の方の多くが論文のリジェクトを経験され、ショックをお受けになることもあるかとおもうのですが、モチベーションを維持してどのようにして次の一歩を踏み出すのでしょうか?
留学時代に修士論文を書き上げた後、その内容を論文としてはじめて投稿しました。その論文は3回くらいリジェクトされ、何度も書き直しました。その結果、修士論文を基に書いた最初の原稿と、最終的に論文として出版したものは、中身が半分くらい違うものになりました。
実際、リジェクトされて、レビューアーからコメントもらって書き直していくと、どんどん良くなっていくんですね。自分が甘かった点や、表現の仕方など、何度も何度も見直していくので、良くなっていくのがわかります。
リジェクトされたり、色々なコメントを頂いたとき、確かに次のステップに進むのは難しいのは事実です。例えば、第三者を入れて書き直したりする方法もあります。レビューアーは著者が気がつかない視点でコメントをしてくる事が多くあり、改善するという意味では役に立ちます。第三者的な目で物を見れるのは大きいと思います。
今後の抱負は?
日本において、薬剤師の業務評価、薬剤疫学、薬剤経済学などの研究分野は比較的新しいものなので、知識や経験を積み重ねて行く必要があります。そのため、将来の研究につながるような基盤整備や人材育成などに取り組んでいます。私の研究ポリシーの一つとして、すべての研究プロジェクトを論文化し、公開をしていきながら次の研究の参考になるようにしています。また、若手の研究者をどのようにして育てたらいいかということをいつも気にしています。アメリカで教育を受け、研究の手法を一から学んだ自分自身の経験を生かして、この分野の研究者を育て、研究仲間を一人でも多く作れたらと思っています。若い人材を育てないと研究も発展しないですし、その人たちと一緒に研究活動を行って、多くの論文を書いていきたいと思います。
若手の研究者の方へのメッセージを
研究するプロセスを是非勉強してもらいたいと思います。1番大事なのは、疑問を感じた時に、そのままにしないで、それを研究という形に落とし込こんで、解決方法を見いだすということです。どうやって研究計画をたてるか、どういうデータを集めて解析するのかということを勉強すると、日常的な臨床現場である疑問に直面した時に、解決方法を自ら見いだすことができる、ということにつながっていくじゃないかと思っています。医療者の一員として薬剤師の教育の中でそういうものを教えていきたいと考えています。
最近興味を持っていること:留学中は多くの英語論文を読まされましたが、日本語に接する機会があまりありませんでした。その反動か、帰国後は活字中毒になり、日本人作家が書いたミステリーを中心に乱読中です。今は、電子書籍や新聞記事が手軽に読めるようになり喜んでいます。明治薬科大学・公衆衛生疫学教室 ホームページ




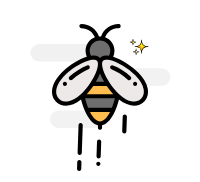



コメントを見る