- 専門家
- 人気
「学術界では査読の変化に対する抵抗が強いようです」

本インタビューでは、若手研究者の視点をお届けします。テナント氏は博士課程の大学院生として研究を行い、論文出版や学会への出席に加え、世界中を旅して研究者を対象としたオープンな研究・科学政策についての啓蒙活動を行なっています。また、活発なブログ投稿や査読のほか、その他の活動―例えばこのインタビューへの対応―も行なっています。テナント氏は、専攻の変更も厭わず、子供の頃から大好きだった古生物学の研究に飛び込みました。その過程で、科学コミュニケーションと政策に関するあらゆることへの関心、とくにオープンサイエンスへの情熱を自覚しました。テナント氏は、ネットワーキングの真の潜在力を現実化し、それを利用して学術研究の重要事項に関する対話に積極的に参加しようとする研究者で、厳しい研究スケジュールを管理しながら、さまざまな活動に取り組んでいます。今回は、研究やその他の分野で興味を持っていることについてお話を伺いました。とくに、本格的な研究活動とその他の活動の両立についてお聞きしました。科学や学術出版の重要な進展について、より多くの人々が知るべきだという強い思いが、テナント氏の仕事への原動力になっているようです。
テナント氏ヘのインタビュー・シリーズ第2回目の今回は、彼が情熱を傾けているテーマ:オープンアクセス、オープンデータ、科学コミュニケーション、オープン査読、インパクトファクターの撲滅(!)についての見解を伺いました。また、科学コミュニケーションと政策に関する意見や情報の交換を促す活動にどの程度関わっているのかについてもお聞きしました。学術界で気がかりな問題として挙げられたのは、研究者にオープンアクセスとその意義についての知識が欠けていること、インパクトファクターが誤用されていること、新しい査読システムの導入に対する恐れがあることなどです。テナント氏は、科学社会における自らの立場や、科学コミュニケーションの推進役(ファシリテーター)としての自らの役割について、研究者らがもっと積極的に関わっていく必要があると主張しています。
テナントさんのLinkedInのプロフィールを見ると、「地球科学に関する学術研究、アウトリーチ、政策立案の相互関連性を高めること」を目指すと書いてあります。その目的をどのように達成しようと思っていますか?
私は、科学コミュニケーションや、政策立案プロセスと科学との関連性を理解すること、そして研究とコミュニケーションにおけるその他の側面の重要性を強調し続けています。例えばインペリアル・カレッジ・ロンドンではScience Communication Forumの運営を手伝いましたが、そこで研究政策の重要な側面である、オープンアクセスやオープンデータの進展についてのワークショップやイベントを開催しました。また、皆さんに研究プロセスについて知ってもらうため、新しい研究や、博士課程の院生としての経験について、あらゆる機会を捉えて執筆活動をするようにしています。政策関連の仕事は最近少し停滞気味ですが、それは単に時間の制約によるものです。それでも地質学会科学委員会 (Geological Society’s Science Committee)のメンバーなので、少しは貢献できることを嬉しく思っています。最近は、研究の透明性についての関心が高まっています。とくに、「オープンサイエンス」の進展状況に注目しています。研究者がこのテーマについてできる限り適切な情報を得られるよう、これまでに5年間ほどを費やしてきました。また、博士課程の後半に入ってから、オープンな研究と出版のプラットフォームであるScienceOpenの仕事を引き受けました。オープンアクセス、オープンデータ、科学コミュニケーション、オープン査読、そしてインパクトファクターの撲滅などを広めることに多くの時間を費やしています!
ブログ記事で、「(オープンサイエンスは)まだ誤解されているので、OpenConコミュニティのさらなる努力が必要だ」と書いておられます。この点について詳しく説明して頂けますか?
もちろんです!ここでは、オープンアクセス一般について述べています。世界の知識の中心へのアクセスという問題という、この上なく重要な問題に関する議論なのに、いまだにこのトピックについての知識があまりに乏しい人がいることに驚いています。最近、学術界におけるオープンアクセス、経済、より広範な社会におけるエビデンスについてレビューした論文を共同で執筆しました。無料で公平に知識にアクセスできること以上に重要なことはないと思っています。この論文は、私のほかの活動と同様、目的に近づくための小さな一歩です。
1つの具体例として、セルフアーカイビングに対する理解の欠如についてお話ししたいと思います。オープンアクセスはコストが高すぎる、あるいは選択肢が少なすぎるから役に立たないと文句を言う研究者が多くいます。セルフアーカイブは(ホスト費用と維持費を別にすれば)どこでも誰でも無料でできますし、Sherpa/Romeoのようなツールを利用すれば、どのような制限があるのかも簡単に分かります。オープンアクセスはコストが高すぎるといいますが、財政面や学術面における特権階級限定の現在のアクセスを提供するシステムに、毎年80~100億ドルほどの費用がかかることを忘れているのではないでしょうか。そのコストに比べたら、ほんのわずかの費用で誰でもアクセス可能な、オープンな形式で世界中の研究結果を公開できるのです。オープンアクセスについて知れば知るほど、学術出版界が奇妙に思えてきます。現在のシステム維持を擁護する、あるいはオープンアクセスに反対する議論が、ますます脆弱になるように思われます。
一般の人は研究論文へのアクセスを望んでいない、あるいは必要ないと主張する研究者もいます。実際、ベルリンで開かれたイベントで、某大手出版社の広報部長がそう言っているのを聞きました。そのように傲慢で無知なエリート主義の視点では、研究界にいまだはびこっている「象牙の塔」の意識を壊すことはできません。「一般の人」は知識にアクセスする必要はない、望んでいない、あるいは値しないという見方は、卑劣で、誤った情報に基づいた認識であり、何年にもわたるグローバルな研究と努力を無視しているというのが私の見解です。学術関係者全員が、このような見解をなくす努力をしていかなければなりません。
ブログの別の記事で、「インパクトファクターや商業出版社がシステムを独占している状態からは脱しつつある」ものの、「インパクトファクターは好むと好まざるとにかかわらず、品質の評価基準としていまだに利用されている」と書かれています。これについて詳しく説明して頂けますか?
インパクトファクターとジャーナルのランキングは、学術界を破滅に至らしめるものだと思います。大学の教員たちの利用頻度が高いジャーナルを図書館員が選べるようにと考えられたのがインパクトファクターですが、今では研究者とその研究を安価に手早く評価する方法として使われています。知識とエビデンスの探究者であるはずの研究者が、学術界の構造を決定する重要物とみなされているこれほどにも脆弱で無意味でかつ誤用されているメトリクスに頼らなければならないのは皮肉としかいえません。インパクトファクターは再現さえできないため、基本的にはトムソン・ロイターと出版社との交渉によって「持ち込まれた」ものだとするエビデンスもあります。どのような形式にせよ、ジャーナル・ランキングを利用することは、学術的実践の貧しさと言えるでしょう。
最近、インパクトファクターを撲滅してより優れた評価システムに移行するために研究者や研究機関がさまざまなレベルで行えることについての提案を行いました。あれこれ議論した末、インパクトファクターを撲滅するだけでは不十分だということが分かりました。まだ評価に利用している人がいる間にインパクトファクターの使用をやめる(あるいは「インパクトファクター・ゲーム」をやめる)のは、危険すぎるのです。現在分かっているのは、インパクトファクターの存在によって、最高の研究者を失う事態になっている、ということだけです。そうした研究者たちは、真の変化をもたらすために最善の研究を行い、それをできるだけ多くの人に伝えたいという思いをもって研究というキャリアの道に入った人たちです。しかし、出世主義のために、学術界はインパクトファクター狩りの様相を呈しており、何を出版するかよりも、どこから出版するかが重要なのだということに気づいて幻滅してしまうのです。これは、科学のためにも科学者のためにも良くないことです。学術界にいる人は皆、インパクトファクターの誤用と支配が継続していることに対し、少なくとも部分的には責任があることを認識し、よりましな代替物を考案できていないことについての説明責任を負うべきでしょう。
学術コミュニティは、査読や出版の代替モデルを受け入れられるほどオープンだと思いますか?代替システムで出版された研究は、従来の方法で出版されたものと同様に正当な研究とみなされているでしょうか?
我々は、グローバルな学術コミュニティが多種多様な人の集まりだということを認識する必要があります。まとまった集団意識のようなものがあるわけではなく、小さなコミュニティの集合体であり、1つ1つがかなり異なっています。そのため、学術コミュニケーションのプロセスに起こりつつある変化への意見は常に多種多様で、両極端に分かれていることもよくあります。
10年前、オープンアクセスは嘲笑の的でした。伝統的出版社はそんなものうまくいくはずがないと言い、研究者は質の低い論文の集まったゴミ箱のようなものだと考えており、助成金もごくわずかでした。現在では、オープンアクセスの方針や規定がグローバルなシステムで定められており、当初強硬に反対していた人も、今ではさまざまな理由によってその多大な利益を認識するに至っています。学術界が常に求めるものは、エビデンスです。「そのシステムがうまくいくということを示してみせてくれ」ということです。オープンアクセスがこの段階にたどりつくまで、すなわち従来のシステムよりも効率的で高品質で安価で、おおむね優れており、またビジネスモデルとして維持できるということを示すまでには、しばらく時間がかかりました。今では、オープンアクセスに特化したジャーナルや、オープンアクセスを義務化している研究助成機関も多く、出版におけるイノベーション(そのほとんどは学術界自体から生み出されたもの)も増えており、さらなる利益を上げる出版社も出てきました。しかし変化は遅く苦しいもので、ここにたどり着くまでには、大変な苦労をしながら何年も交渉を重ねる必要がありました。正式な査読を受ける前の段階の論文を効果的に即時出版するという「プレプリント」などには、まだまだ議論が必要です。高エネルギー物理学や数学などのように、この手の議論を何十年も続けている研究コミュニティもあります(実は、インターネットが発明されたのはこれが理由なのです!)が、生命科学の分野では、さまざまな理由から、少し遅れています。ただ、速度は遅くても、少しずつ変化は起こっており、新しい出版や伝達の方法で実験することを楽しんでいる研究者もいます。変化の受け入れにオープンな研究者もいますが、保守的な人も多く、今後どうなっていくかは、社会的規範や実践、政策、選択肢の有無など、数多くの要因が絡み合って決まっていくことでしょう。最大の問題は、潜在的な利益よりもリスクの方が高い場合も多いということです。研究者が、オープンであることと自分のキャリアとのどちらかの選択を迫られる立場におかれることは、何としても避けなければなりません。
私が博士課程に入ったばかりの頃、「オープンアクセスだけの出版で研究者としてのキャリアを積んでいくなんてできっこない」と何人かの同期に言われました。(この後日談は後で紹介します。)私の最初の論文がPeerJから出版されたとき、先輩研究者からは「インパクトファクターもないんだから、意味がない」と言われました。これには傷つきました。2番目の論文はPLOS ONEに掲載されましたが、このときも別の先輩研究者に、「査読がないから意味がない」と言われました。これは2014年でしたから、まだ最近のことです。これらのコメントを忘れることができないのには、いくつか理由があります。2番目のコメントは明らかに間違いで、オープンアクセスに関する理解が根本的に欠如していることを示しています。最初のコメントは、ジャーナルを中心に据えたままで、新モデルへの移行を目指して学術出版システムをいくら変えようとしたところで、研究そのものの質と研究の伝達や研究者の評価(これはジャーナル名とインパクトファクターによってほぼ決まってくる)を切り離すことはできないということを示しています。これが本当に重要な点で、学術界の構造改革をせず、出版だけを改革していても十分ではないことに多くの研究者が気づき始めたのです。それから3年後、査読付きで出版された私の論文9本は、すべてオープンアクセスで出版されましたが、そのおかげで名誉ある学部賞を受賞するという幸運にあずかりました。反対派の人々に、どうだ!といってやりたいですね。
査読に関しては、まだオープンアクセスほど議論が出尽くしているとは言えないようです。Mozilla Global Sprintで、ウェブサイトの力をよりうまく利用した、将来的に可能性のある査読モデルとはどのようなものかについて、共同で論文のドラフトを書き始めました。これはかなり進歩的で想像力を必要とすることですが、学術界では、査読の変化に対する抵抗が強いようです。現在上級研究者の地位にある人は、今の査読システムと伝統的な出版形式でうまくやってきました。そうでなければ今のような地位にいないはずです。ですから、このような人たちが、そのシステムに亀裂を入れるような考えをよく思わないのは当然です。問題は、上級研究者の中でもさらに上の、権威ある地位にいる人々に、大規模な変化の動向だけでなく、人々の内面にまで影響を及ぼす力があるということです。これは、オープン査読について話をすればより明確に分かります。若手研究者にオープン査読のことを話すと、ほとんど全員が恐怖感をおぼえるのです。それは皆同じ理由、つまり「記名式で査読を行うと、上級研究者が自分の査読を快く思わなかった場合、その反動で自分のキャリアに悪影響が出るかもしれない」ということです。これは権力というダイナミクスの乱用であり、査読システム自体とは何の関係もありません。上級研究者は説明責任を負わないままシステムを統制し、ゆがめることができるままになっている、という事実が問題なのです。ですから、力を握っている側の、現状を維持しようという強固な保守体制と、査読や学術コミュニケーション一般に関してよりまっとうな展望を持っている人々との間では、常に戦いが繰り広げられています。問題は、変化を望む人(例えば学生など)にはもっとも危険にさらされる人が多く、現在のシステムに収まっている人々は、そこで利益を得てきたために変化への動機がほとんどないということです。学術界の「文化的惰性」について言う人は多いですが、これがその大きな要因になっていると思います。
研究者が、科学コミュニケーションや科学政策における現在の動向について知っておくことは重要でしょうか。
研究者は、研究を行うことで給与をもらっています。研究が研究者の最優先事項であることは確かですが、自分を取り巻く世界が変化しているのに気づかずに研究を続けるのは愚かです。研究者があまりにも情報に疎いのを知ってがっかりすることもあります。例えばインペリアル・カレッジ(やその他の機関)でも、全国的なオープンアクセス方針が新たに制定され、オープンアクセスに特化した助成金や公共リポジトリまでできたことを知らないという研究仲間がたくさんいました。出版の寡占という問題、つまり自分たちと同じ水準で研究へのアクセスができない人がいるという事実や、毎年出版社に支払わなければならない金額などについて考えたこともない、という人が大勢います。「自分には必要な研究へのアクセス権がある。一体何が問題なんですか?」ということを何度も言われましたが、きわめて腹立たしいことです。インパクトファクターの計算方法や、研究データを共有する方法や理由、その他さまざまな側面における学術コミュニケーション環境の変化を分かっていない人もたくさんいます。ただ、たいていはもっと学びたいという姿勢なので、その点は素晴らしいことだと思います。もっと学べるように活動し、変化をもたらすことを奨励し、自分のまわりに賛同者のコミュニティを作っていこうとする人が必ずいるのです。だから私はOpenConが大好きなのです!
でも、順調にいかない要因もいくつかあります。それは第1に、学術コミュニケーションのさまざまな面に関する知識を研究者が個人で身につける状況であること、第2に、大学や研究機関がこれに関するトレーニングを提供していないこと(つまり、複雑で急速な進化を遂げている領域だということです)、そして第3に、研究コミュニティがこれらの事項についてより高度なレベルでオープンに議論をしておらず、自分たちの行なっていることが常に公共の利益と研究の伝達や普及に貢献しているかを確認していないことです。
すべての研究者とその研究に影響を与えるような大規模な議論は常にあります。例えば、EUの著作権改革や、2020年までにEUの助成で行われたすべての研究をオープンアクセスにするという提案があります。私が話をする研究者の中には、出版社に著作権を譲渡する署名をしたら、自分の研究の所有権がなくなることすら分かっていない人が大勢います。このような単純な事実を明らかにすると、おおいに戸惑い、信じられないという人が多いのです。出版社は、自分たちがなるべく利益を得られるような形でこれらのシステムの変化を促すロビー活動に精を出すでしょう。研究者としては、まずはこれらの変化を理解するために必要な知識を身につけ、さらには自分たちの意見を広め、変化に影響を与えるプラットフォームを持たなければ、何もできません。
テナントさん、研究と学術出版の重要な側面に関する見解を共有してくださり、ありがとうございました!
インタビュー最終回では、新米研究者への貴重なアドバイスと、学術出版の将来についての展望を伺います。
テナント氏へのインタビュー記事:
- Part 1: 「研究では、自分が心からやりたいことを追求すべきです」
- Part 3: The future of academic publishing and advice for young researchers



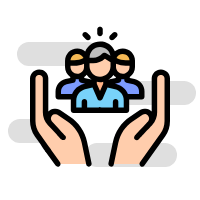




コメントを見る