「査読の多様性は身近な問題だと感じます」―南アジア人女性の視点

(注: こちらは、2018年に初公開された記事です。Peer Review Week 2021に際し、再発行しています。)
学術出版界で活動する南アジア人の女性として、査読の多様性に関する問題は、専門的にも個人的にも身近なものだと感じます。研究における学習、リソース、ネットワークへのアクセスは、当然視されてきた(されている)バイアスや思い込みの影響を受けています。その結果、周縁化された集団は、研究と査読のサイクル全体でさらに押し出されることになるのです。
バイアスの要因が、性別、民族、年齢、地理的条件にあることは、研究で十分に示されています。また、研究そのものと研究結果の質と頑健性は、多様性によって高まることも示されています。多様性に乏しい状況は、効果的な査読プロセスを危機にさらすだけでなく、査読が支え強化している研究界全体をも危機にさらします。たとえば、南アジアの若い女性科学者を査読者から除外すれば、彼女たちは、専門知識を高めて分析と執筆のスキルを伸ばす機会を奪われます。そうすると彼女たちは、査読経験をアピールして学会への招待状や助成金の獲得につなげることができません。査読経験をアピールすることができれば、コラボレーションの機会を得て、研究の可視性をもっと高められたかもしれないのです。このことは、ゆくゆくは彼女たちのキャリアアップと職業の継続に影響を与え、同質的な既存の覇権がさらに強化されることになります。
ジャーナルはどうすれば査読の多様性を実現できるか?
研究とその評価における多様性を拡大・維持することには、大きな価値があります。無意識の偏見を克服するために意識的な取り組みを行うことが、ジャーナルが基盤とする出版社、学会、研究機関に求められています。
まずは、バイアスが存在することを知り、認めることです。バイアスは、現在の研究システムと社会システムにおいて避けられないものです。それを踏まえた上で、積極的かつ継続的にバイアスに対処する必要があるでしょう。
ジャーナル、学会、資金提供者、出版社における性別や地理的分布の状況などを調べる多様性の監査は、効果的な出発点です。監査を実施したら、調査結果に対処し、結果に影響を行使することが必要です。
また、多様な査読者を見つける際の供給ギャップを埋めることも必要です。具体的には、研究活動における多様性を奨励してバイアスと戦う、査読ができるように研究者を訓練する、といった意識向上対策が挙げられます。出版社は、ここで重要な役割を果たすことができるはずです。編集委員会や諮問委員会や著者の多様性を促進するのと同様に、ベテラン研究者によるメンタリングを促せば、学術コミュニティやオンラインハブが活性化につながるでしょう。Taylor & Francis社では、編集者がジャーナル編集委員会に対し、研究コミュニティの多様性を反映するよう働きかけと支援を継続することで、まさにこれを実行しています。また、研究における地理的変化を反映するために、中国とインドの査読者のスキル向上にも取り組んでいます。こうした対応は、将来的に中国とインドが安定的に研究界を率いるようになったときに、より多様で包摂的な研究環境を整える準備になるでしょう。
このように、能力開発、意識の向上、ギャップを評価して進歩を促す継続的チェックと監査は、いずれも査読の多様性の向上につながる手段と言えるでしょう。



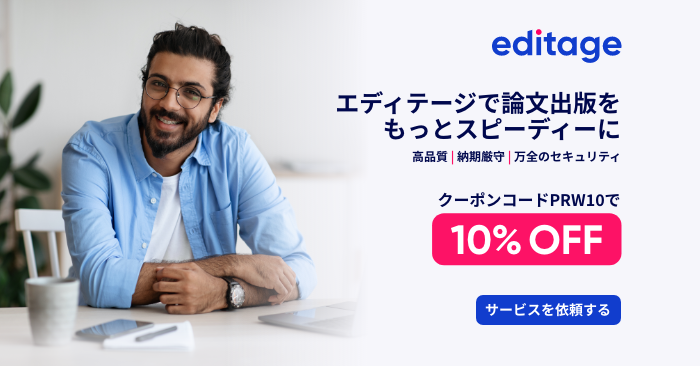
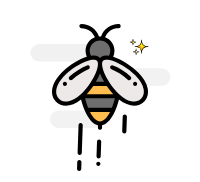



View Comments