- 専門家
- 人気
日本医学コミュニケーションセンターの先駆者 バロン教授インタビュー②「日本における医学英語-専門家はいかにコミュニケーションをとっているか」

J.パトリック・バロン(J. Patrick Barron)教授は、the Journal of Gastroenterology、Breast Cancer、the Journal of Bronchology、Allergology International、the Journal of Cardiac Surgeryといった幅広いジャーナルでエディターや編集顧問をされています。
1975年、日本の医科大学に情報センターを作るというアイデアを初めて提案されました。それにより出てきたのが、医学情報センター、医学論文に対するセンター内サポート、日本国内から外国への情報のコミュニケーションといった革新的なアイデアです。今回そのバロン氏にお話を聞きました。
東京医科大の国際医学情報講座(Department of International Medical Communications ;DIMC)主任教授として、日本で「医学英語」教育を進めて英語の目標・目的にしていることと、それを達成するための行動指針について、詳しくお話していただけますか。
第一に、ご質問されていることは医学英語に関することですね。医学英語の存在理由を定義する必要性をご指摘されるとは鋭いご質問です。私が日本に来た頃は、医学英語というようなものはありませんでした。私は全くの素人でしたが、論文を編集する経験により、私と著者の間に非常に大きな隔たりがあることにきづいたのです。論文の著者は、その分野に関する専門用語を操っていましたが、最善の方法では使っていなかったようです。素人にはわからないことを伝え合う方法があることに気づくようになりました。
幸運なことに、指導してくださった早田義博教授が日本の外科学と呼吸器病学の分野では有名な方で、アメリカと日本の間で行われた、肺がんに関する非公式の会合に多く招待されていました。会合は日本とアメリカで一年おきに交代で開かれ、主催国ではない方から約12名の専門家が招へいされ、主催国からは約20名の専門家が参加しました。おっしゃっていたように、こっそりと聞き耳をたてることで、私は、専門家が互いにいかにコミュニケーションをとっているか理解できるようになりました。それは普通の人の議論の仕方とは異なっているのです。

バロン教授と故早田義博博士、アン王女、ジョン・カルース博士
さて、1972年までちょっとさかのぼらせてください。この年、私は早田教授と、日本で英語の医学教科書を出版している一流の出版社から、肺がんについての図録を翻訳するよう依頼されました。報酬はありませんでしたが、大変光栄に思ったものです。けれども、2,3日考えた後、このプロジェクトを公平に扱うことができないと判断しました。国際的な読者が必要としているテーマを詳しく述べることができるか、自信が持てなかったからです。ですから、お断りしました。けれども、早田教授は、ダイレクトにこう言いました。「私たちが教えましょう」と。それからというもの、毎週金曜の夜に伺い7時から10時半、あるいは真夜中まで、早田教授と5、6名のスタッフに教えてもらったものでした。彼らは、レントゲン写真、病理学上の発見、当時新しく開発されたファイバー内視鏡、彼らの患者の切除された標本の写真を見せてくれました。私はほんの翻訳という非常に公正な仕事をしたと思いますが、出版されなかったとことに、後で安心しました。といいますのも、病理学のセクションを担当していた著者たちの1人が、自分で英語を書くと言い張ったからです。けれども、その人は病理学では非常に有名で、多忙を極めたため、そこまで手が回らず、結局本は出版されなかったのです。
肺がんに関する、アメリカと日本の委員会に出席した時まで、2、3年話を進めましょう。壁にとまっているハエのようにひっそりと、早田教授や彼のスタッフに肺がんについて教えてもらい、やがて私は彼らが言っていることのほとんどを理解できるようになりました。私はまだ医学部に行くことを利用していなかったので、口頭によるコミュニケーションや、また書き言葉によるコミュニケーションで使われている「医学的な」表現のタイプを習得する機会はありませんでした。
そのことにより、医学の専門家に英語を教えることが実際に必要とされていることに気づき、1980年聖マリアンナ大学医学部で助教授になった時、私はいわゆる医学英語(それ以来、他の言葉で呼んでいません)の導入を始めました。大変支持してくれる人もいれば、臨床医を含め、「明らかに馬鹿げたことをしている、医学英語なんてものはない、ただの英語だ」という人もいました。私はそんなことはないとうことを、自分の目で見、耳で聞きました。医師が互いに話したり、論文を書いたりする場合と、人文科学の大学院生が論文を書く場合とでは、やり方が違うのです。医学部の学生に自分の専門分野で他の人とコミュニケーションをとれるだけの十分な英語を教える課程を設立するのに専念したのもそれが理由です。こうした課程は、その後日本国内で広く採用されるようになりました。
医学部の生徒全員がこうした機会を与えるべきだと私は思っていました。そうした機会を利用する、しないは本人に任せるとしても。けれども、学生が利用できる、同一の、役に立つ、実用的なカリキュラムを作るのは、教師次第なのです。そのため、私は1982年、医学英語の教師による団体を設立しようと試みました。
私は日本中にある医学部の教師約450名に質問紙を送りました。切手を貼った返信用封筒も含めて郵送料はすべて自腹です。医学部の学生への医学英語教育に関する研究団体あるいは学会への参加に興味を示したのは、450名のうち、私自身も入れて4名でした。がっかりしたこと、この上ありませんでした。全国でたった4人。日本の地理をご存知でしょうか。そのうち1人は本州、北海道と四国と九州に1人ずつでした。私が思い描いていた支援とは全くかけ離れた結果です。率直に言って、一番の問題は、医学部の英語教師の多くが、正規の大学の英語科では職に就くことができなかったということ、そのため、全く新しい分野で引き受けるというような知的な冒険を行うのを非常にためらっていたということです。特に、英語教師の多くは、もし学生に医学書を誤って教えたら、患者に悪い影響を与える、あるいは死に至らしめてしまうのではないかと心から信じていたと思います。
このように、医学のための英語という構想を取り巻く雰囲気は非常にネガティヴなものでした。そして、それこそ私が克服しようと思っていたものです。私がやったのは、本物の医学教科書を使うことでした。半医学英語と私は呼んでいましたが、そういう英語を教えるため欧米で手に入るタイプの教科書ではありません。普通の英語とは若干異なるように思われますが、医療の専門家が話す英語そのものではありません。互いにコミュニケーションを取ろうとしている臨床医のただ中にいるという状況に置かれたことはラッキーでした。
私は問題点を理解し、内視鏡検査に関する国際会議で発表したビデオを学生に見せることで、乗り越えようとしました。学生に見せた内視鏡のビデオでは、会議の模様を私自身が翻訳し、ナレーションしました。医師でないのに医学を教えることで非難されることがないよう、私は細心の注意を払わなければなりませんでした。自分が翻訳し自分がナレーションをしたことを教えているのです、と伝えました。
実際、その点については問題はなく、構想は徐々に強くなりましたが、学会を現実に立ちあげるのに必要だったのは、私自身より臨床的な影響力をもっと持つ誰かであり、その誰かとは、神経外科医の植村研一氏でした。また、医学出版社、製薬会社、医療機器メーカーからも多大な支援を受けました。植村氏の学会、日本医学英語教育学会(Japanese Association for the Study of Medical English Education;JASMEE)には非常に早くから参加しました。今では会員数500名で、50%が臨床医、50%が言語畑の人です。医学部の大学院生を、自分の分野において英語でコミュニケーションをとれるレベルまで引き上げるためには、統一的なカリキュラムあるいは一連の単元をうまく使う必要があります。この学会によって、そうしたカリキュラムや単元を開発する効果があがることを期待しています。
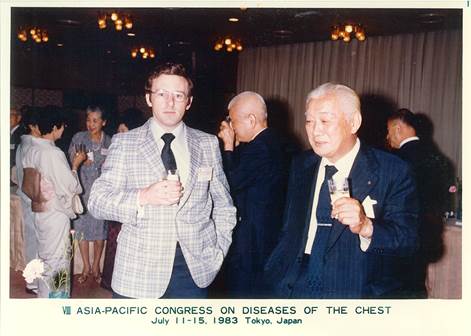
バロン教授、故戸栗栄三氏(聖マリアンナ医科大学学長)
教授のご経歴(スコットランドで生まれ、日本語を学び、東洋・アフリカの研究を専攻)と、現在の研究(医学英語コミュニケーションについて、ヨーロッパ、北アメリカ、中国、韓国と広く講演を行っています)から、長年にわたり国際的な視野をもっていらっしゃったことが非常によくわかります。DIMCでは、世界中へと医学英語教育をグローバル化するために標準化されたカリキュラムを作っています。先生のお考えでは、こうした国際的統合の利点と、様々な地域が統合までの過程で乗り越えなければならない問題点について、先生のお考えを聞かせてください。
医学英語についての標準的で統一されたプログラムは、世界中の医大(医学部)で必要だと思っています。EUが始まり、EUのどこかの医学部を卒業すればEUの別の加盟国で開業が可能ということからも、こうした標準化されたプログラムが重視されていると思います。つまり、スウェーデンの医師が、フランスでアルバイトすることができ、ドイツの医師がイギリスでアルバイトできる、という意味です。良いことですが、言葉の問題もあり、深刻な事故が起きた例や、実際に死亡者が出た例もあります。
後者は、ヨーロッパ大陸からイギリスに来た医師たちが、薬の名前は似ているが成分が異なっていたことから、薬名や用量を間違えたというケースです。もっと重要なのは、東ヨーロッパ、中国、韓国、日本、インドシナ、アフリカ、南アメリカでは活性化されないままでいる大量の情報にとって、こうしたプログラムが不可欠だということです。こうした地域や国は、患者さんが利益を受けられるような国際的論文の世界に足を踏み入れるという点では、まだ日の目を見ないでいるのです。
最終的な目標は、患者さんの利益です。審査者の側ではそうした意識がかなり欠けています。論文の読者がたまたま英語のネイティブではなかったら、論文の科学部分に関する判断があいまいになってしまいます。ですから私は、東京医科大で標準化されたカリキュラムを研究しているのです。特に、ハンガリーにあるペーチ大学の、レベク・ナジ教授、ワルタ教授、その他ヨーロッパの仲間は、ヨーロッパの医療専門家に対する医学英語のテスト・教育の統一的なシステムを作ろうとしています。
次回、J.パトリック・バロン教授とのインタビューの最後の部分が続きます。
論文著者にとって役立つ内容ですので、どうぞお楽しみに!.
記事はこちらから。








コメントを見る