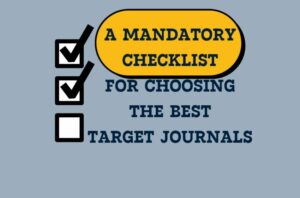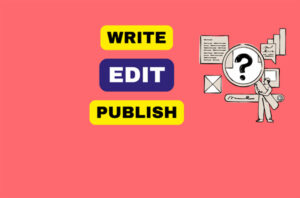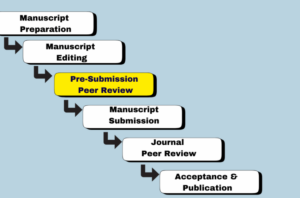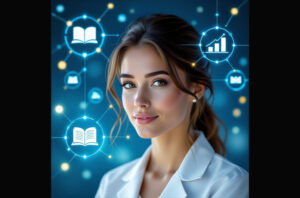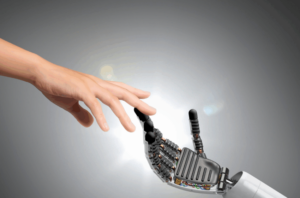今回ご紹介するのは、Editageコミュニティの一員であり、研究者として、そしてメンターとしても精力的に活動するアスリ・テリ准教授です。 中には、「研究者にとって査読とは何か」についての彼女の洞察を読んだことがある方や、「若手研究者は査読者にふさわしいのか?」という2021年のPeer Review Weekウェビナーで彼女の話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
アスリ・テリ氏は、南アフリカのウィットウォーターズランド大学WISERにてリモート・フェローシップを通じて研究員を務めています。ヨーロピアン・グラジュエート・スクールとアパラチアン州立大学の博士課程で、メディア・コミュニケーション分野の学位を取得。これまでにトルコ、スイス、マルタ、フランス、ドイツ、アメリカなどの大学で、国際大学院生の指導・教育に携わってきました。Academics for Peace(ドイツ)、EDRi(ヨーロッパ・デジタル権利団体)、Digital Freedom Fundなどの活動にも参加しています。
彼女はこれまで、形式的・非形式的なメンタリングの両方を経験してきました。研究者にとって、メンターは学術のさまざまな「迷路」を進む手助けになると語ります。そこで今回は、彼女に「学術界におけるメンタリングの役割」について話を聞きました。
メンタリングの役割とは?
多くの人は、メンタリングが学術キャリアの基盤であると考えています。実際、優れたメンタリングは、優秀な学生や若手研究者(ECR)の育成・定着において重要です。
ただ私は、もう少し控えめな視点を持っています。メンタリングは、研究者に「学問の外にも人生がある」と気づかせてくれる存在だと思います。困難も喜びも含めて、人生を理解しなければ、本当の意味で人間らしく生きることはできません。
よく「ワークライフバランス」と言われますが、私はこの表現に違和感があります。制度の不公平を黙認する響きがあるからです。不当な労働環境があるなら、それを変えていく必要があります。良いメンターは、その意識を高めたり、改善をサポートしたりする存在になれます。メンターは、研究者としてだけでなく、人間として成長を支える存在でもあるのです。
私たちは学術の中だけでは生きられません。だからこそ、定期的に「それ以外の世界がある」と思い出させてくれる存在が必要です。私は「ライフコーチ」という言葉はあまり使いませんが、学術におけるメンターは、似た役割を果たしていると思います。メンターは、キャリア形成だけでなく、精神的な支えにもなるのです。
初期の研究生活にメンターはいましたか?
一人の決まったメンターがいたわけではありませんが、必要なときに相談できる何人かの存在がいました。正式に「メンタリング関係」と呼んでいたわけではないですが、私にとっては大きな支えでした。
特に印象に残っているのは、博士論文の執筆時に助けてくれた副指導教官です。私が「時間がない」「疲れている」と愚痴をこぼしても、彼女は辛抱強く耳を傾け、実用的なアドバイスをくれました。心が折れそうな時期だったので、その支えが自信につながり、研究や教育の場面でも活かせました。
その後、彼女のアドバイスのおかげで、採点の時間が大幅に短縮されましたし、聞く力や忍耐力も鍛えられました。あの時の支えがなければ、今の私はなかったと思います。
メンターになるには、どれくらいの経験が必要ですか?
確かに、メンターという言葉からは、豊富な経験を持つ人物像が浮かぶかもしれません。ただ、メンタリングに必要なものは、その時の相手のニーズ次第です。ときには、経験よりも共感や感情的なサポートの方が重要な場合もあります。
経験豊富な研究者がサポートできる場合は理想的ですが、同年代の仲間が大きな助けになることもあります。また、ベテラン研究者が若手から学ぶこともあります。つまり、キャリアの早い段階でも、メンターになることは十分可能です。
最近では、非公式なメンタリングの機会も増えています。もしあなたが若手研究者で、誰かを支えたいと思ったら、まずはローカルまたはオンラインでプログラムを探してみてください。
メンターとして一番難しいことは?
最初に、お互いの期待やゴールを共有することが大切です。ただ、計画通りに進まないこともあるので、柔軟な姿勢が必要です。最初の段階で期間を決めると、気持ちの整理もしやすくなります。
効率的なプランに、思いやりと共感が加われば理想的です。メンターとメンティーが友情を育むこともありますが、関係が近くなりすぎると、支援に影響が出ることもあります。私の最初のメンティーたちは博士課程の学生で、今も連絡を取り合っています。
メンティーが最大限に学ぶには?
まずは、相性の良いメンターを見つけること。支援が短期で済む場合もあれば、長期的な関係が必要なこともあります。始めにプロセスや目標をしっかり共有しましょう。
メンティー側も、メンターが多忙であることを理解し、毎回の面談に向けて準備することが大切です。苦難を乗り越えるためのちょっとしたコツでも学んでおくと、後で役立つでしょう。
また、お互いが率直に意見を交わせる関係を築くことが重要です。何か違和感があれば、遠慮せずに伝えるべきです。
現実的な目標を設定できれば、有意義なメンタリングが可能です。あるメンティーは、私との6カ月の関係のあと「今度は自分が誰かの支えになりたい」と言ってくれました。その言葉がすべてを物語っていたと思います。
アスリさん、貴重なお話をありがとうございました。この記事が、多くの研究者にとって、メンタリングのヒントになることを願っています。
この記事はEditage Insights 英語版に掲載されていた記事の翻訳です。Editage Insights ではこの他にも学術研究と学術出版に関する膨大な無料リソースを提供していますのでこちらもぜひご覧ください。