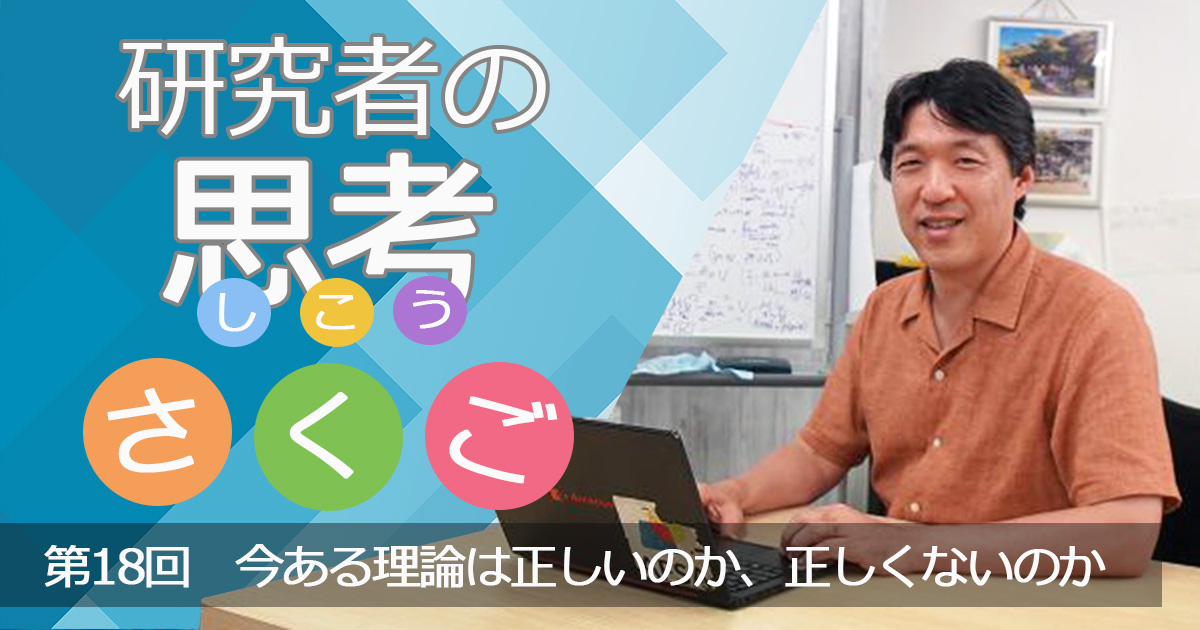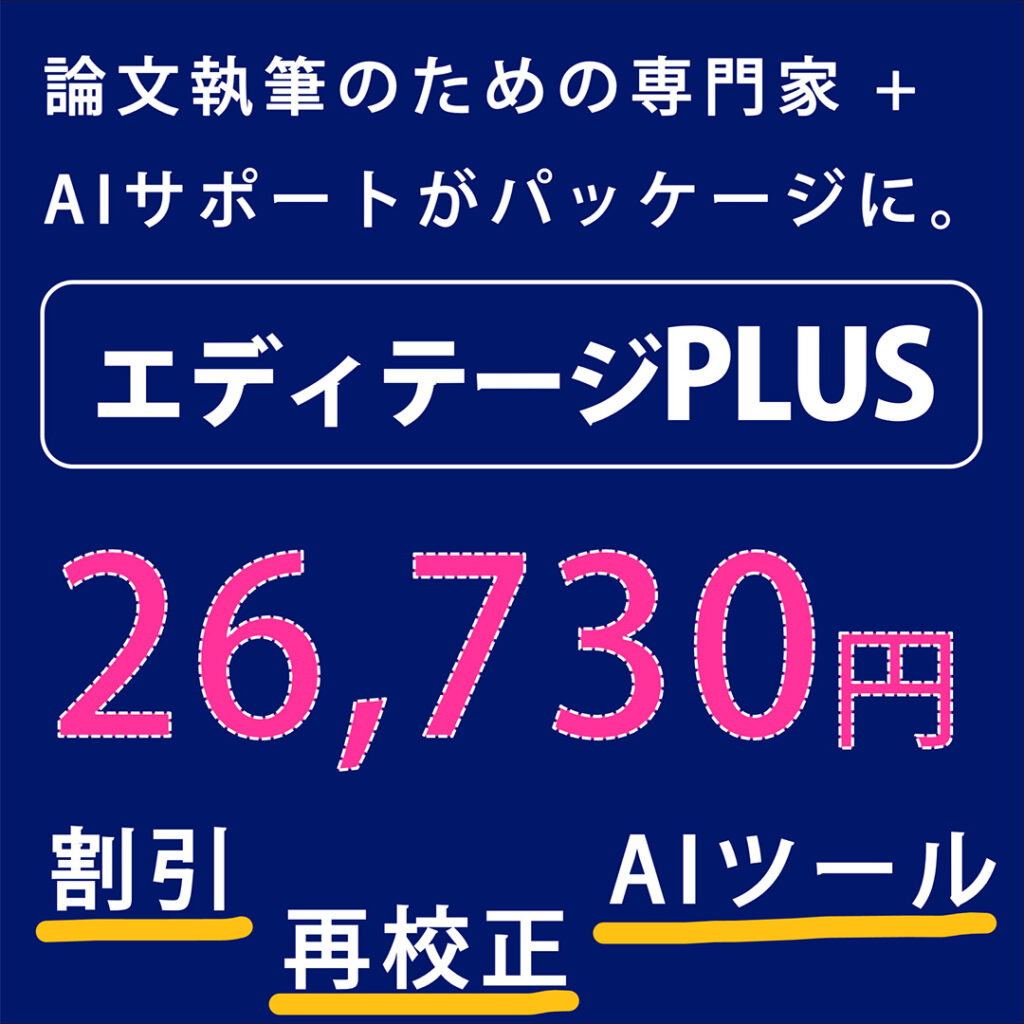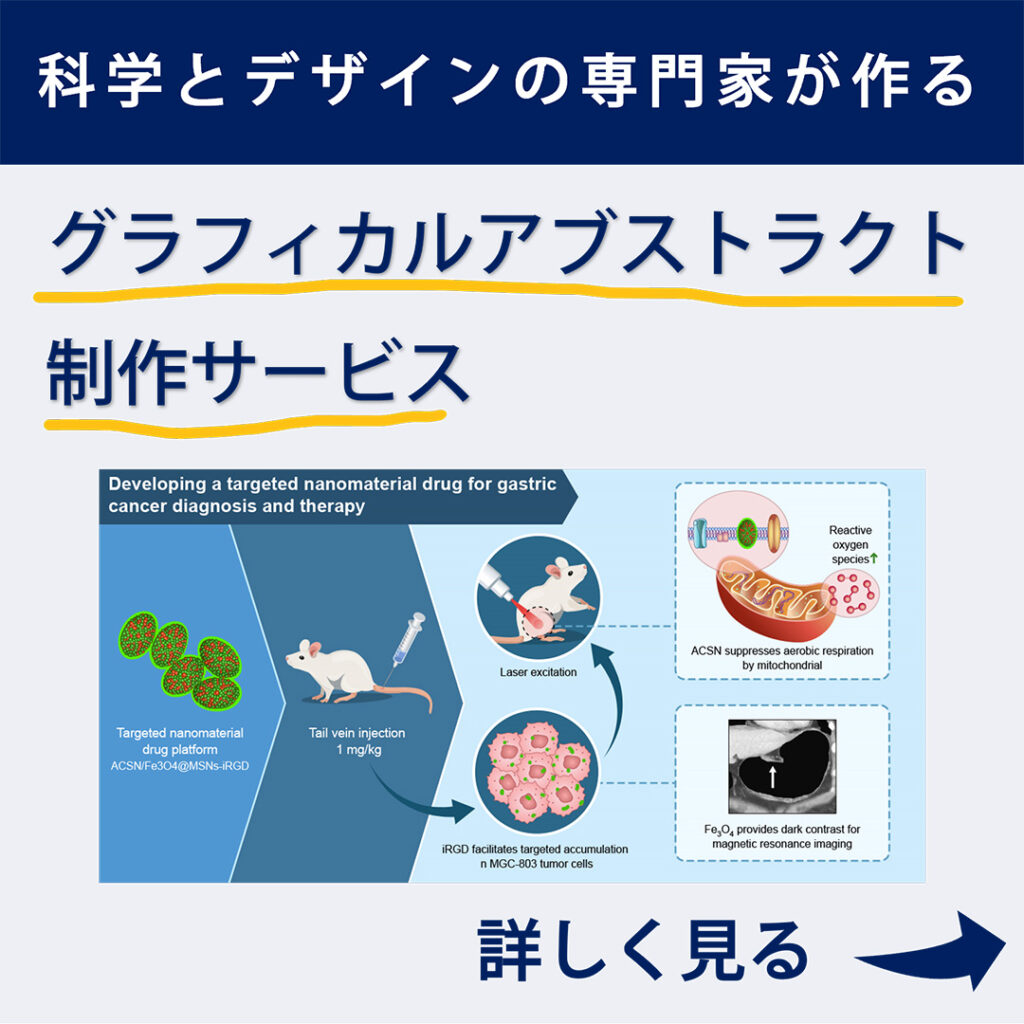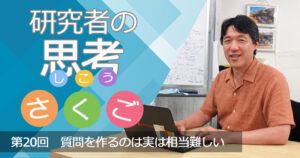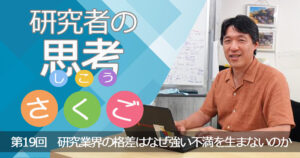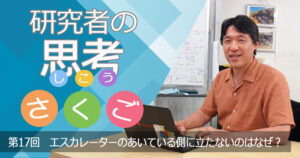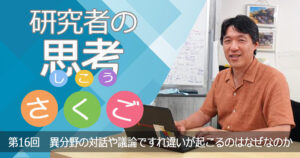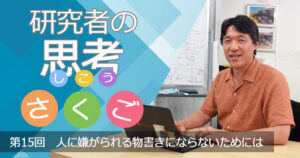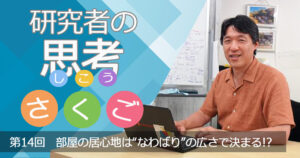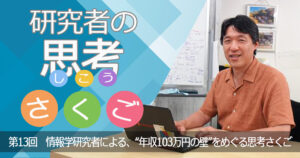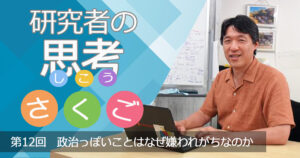学問にとってなくてはならない「理論」ですが、皆さんはどんなイメージを持っていますか? ともすれば絶対的なものと考えられがちな「理論」ですが、学問によってその見方は違ってきそうです。連載・研究者の思考さくご第18回では、国立情報学研究所の宇野毅明(うの・たけあき)先生に情報学研究者ならでの視点で、なぜ学問によって「理論」の見方が違ってくるのか、考察していただきました。
先日、物理学の研究者と雑談していたときに、「現在の物理の理論が正しいと思っている物理学研究者はいない。なぜなら、現在の理論では説明できない現象があるからだ」と言われました。ついでに「正しいと思っている人がいたら、勉強不足ですね」くらいの強いことまで、冗談で言っていました。これはなかなかびっくりでした。「物理学から出てくるものと言えば正しいもの」のようなステレオタイプがあるのに、「正しくない」というのはなんとも不思議な感じに思えるのですが、言われてみればその通りです。目からうろこですよね。
筆者は数学、情報学の理論を研究しているのですが、こういう数理数学の分野では、1回証明されたことが覆ることは決してありません。1回証明された定理は、永遠に正しいのです。物理のほうが世界の真実と関わってそうなのに、ここに違いがあるのはなんとも面白いですね。なぜこんな違いが出るのか、考えてみました。
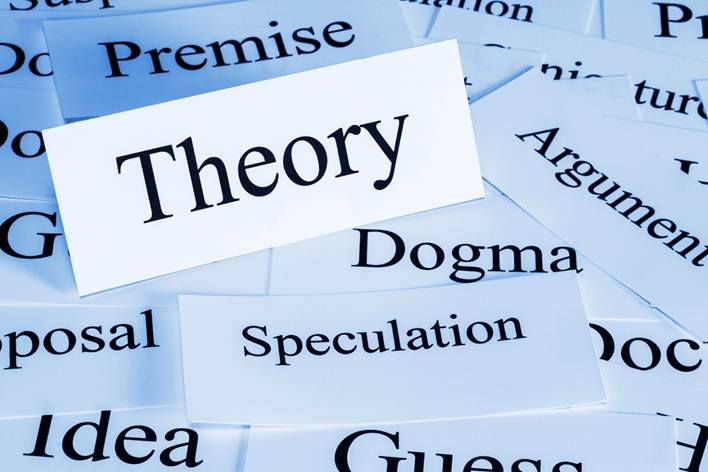
数学も物理も、理論を作っています。ただ、物理は世界を説明するための論理です。ですから、世界が説明できなければ、定理や数式が正しくても、世界の説明としては正しくありません。数学や情報数理(情報学の数学)では、実際の世界ではなく、自分たちで構築した数学の世界を研究対象としていて、その世界で成り立つ定理を研究します。定理として、数式として正しければ正しいのです。物理学は、世界を正しく説明するために、理論を磨いていきます。現在の理論は常に正しくありません。一方数学は、ある種の公理、「平行線は交わらない」などを出発点として、その公理だけから導かれるものを証明していきます。公理から証明できることの世界を広げるのが数学です。他の公理について考えることもありますが、それで昔の定理が否定されることはありません。つまり、数学と物理では何をするのかが違うので、正しさの意味が違うのです。
理論を作ると言えば、哲学も理論を作っています。人の心や社会を対象として物事を考察し、概念化していきますが、このとき、数学の数式のように自然言語での論理を使って論理を導いていきます。人の心や社会は時代によって、地域によって、前提条件が変わるので、昔証明したことが新しい時代でも成り立つとは限りません。哲学も、世界を説明するための学問で、常に完璧とはなりません。また、統計学も、「データは理論的に良い性質を持った分布に従って生成されてできている」という仮定を置くことで、因果や相関などを導き出し、データから世界を説明しようとしますが、仮定が成り立たないことも多く、完璧な説明にはなりません。しかし、確率や分布について数学的に証明されたことに関しては正しさが覆ることはありません。筆者の研究している情報数理も、この側面を持っています。
こうしてみると、数学の考え方、アプローチはかなり特殊なのかと思われますが、数学とそれ以外に学問が分かれるのではなく、世界の説明の仕方に関してある種の軸があるように思います。「①世界を証明しようとするもの、世界をなるべく良く近似する理論を作ろうとするもの」、「②自分で世界を構築し、完璧に解明できる部分を明らかにしていく、あるいは完璧に解明できる世界を構築するもの」の2つがあり、その両者の間に、「③世界を相手にしているが、仮定を置いたり特殊な場合を考えたりすることで、世界の中から完璧に解明できるところを切り出して証明していくもの」というスタイルがあるように思います。①が物理と哲学、②が数学、③が統計学や情報数理という感じではないでしょうか。
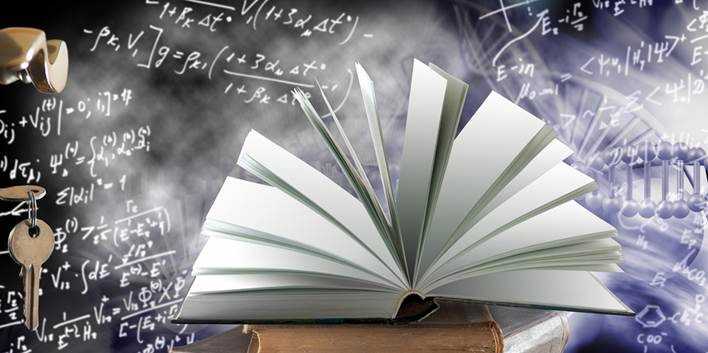
ところで、数学の知人が、同じような文脈で、「ピタゴラスの定理は実世界では正しくない」という言説を提示しています。実世界の空間は重力によって歪んでいるので、実は正しくはピタゴラスの定理は成り立たないと。確かにその通りです。ここで言っているのは、そもそもどのような世界を考えているかという「論理の前提」です。空間が歪んでいないという前提をおけば、ピタゴラスの定理は正しく成り立ちますが、実際には重力の影響で空間が微妙に歪んでいるので、ピタゴラスの定理は厳密には成り立ちません。「前提や論理体系が変ってしまうと、完璧な証明ですら正しくなくなる」ということです。ときに「論理的に正しいがどうか」で論争が起こりますが、ここには、そういうことを言う前に、「まず論理の前提を見るべき」とメッセージが含まれているのです。「数学的に正しい」とか「科学的に正しい」とかを言いたければ、その「論理の前提」が今考えている対象とマッチしているかを考えなければいけません。世界を相手に議論し研究しているつもりでも、実は今議論している世界は、相手の言っている世界とはズレているかもしれないのです。