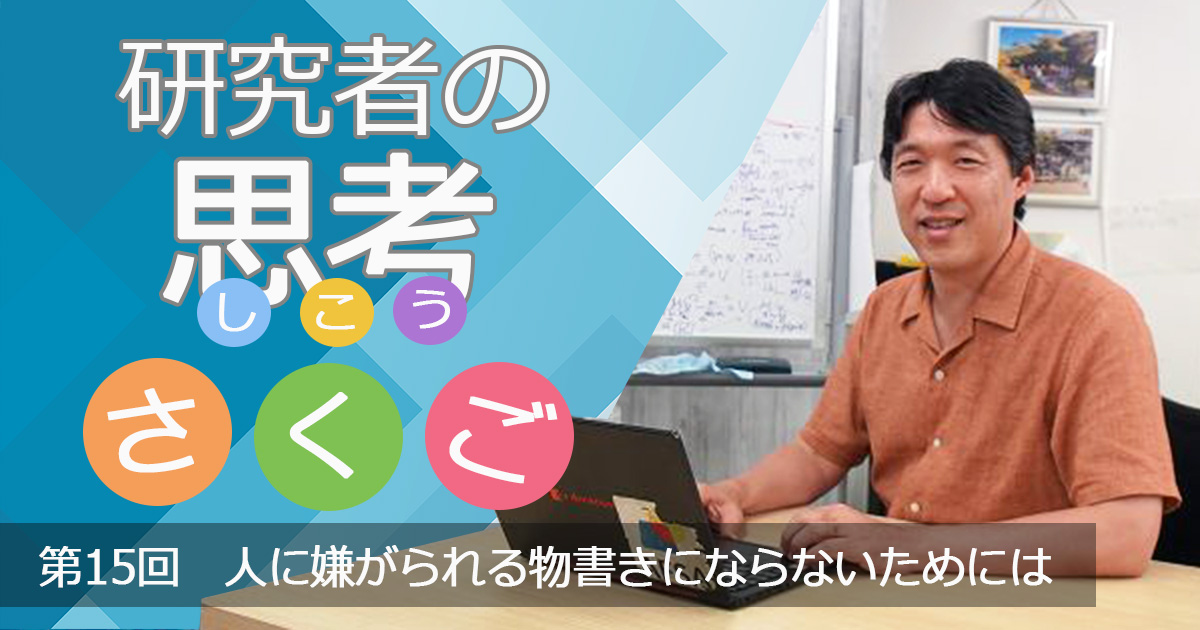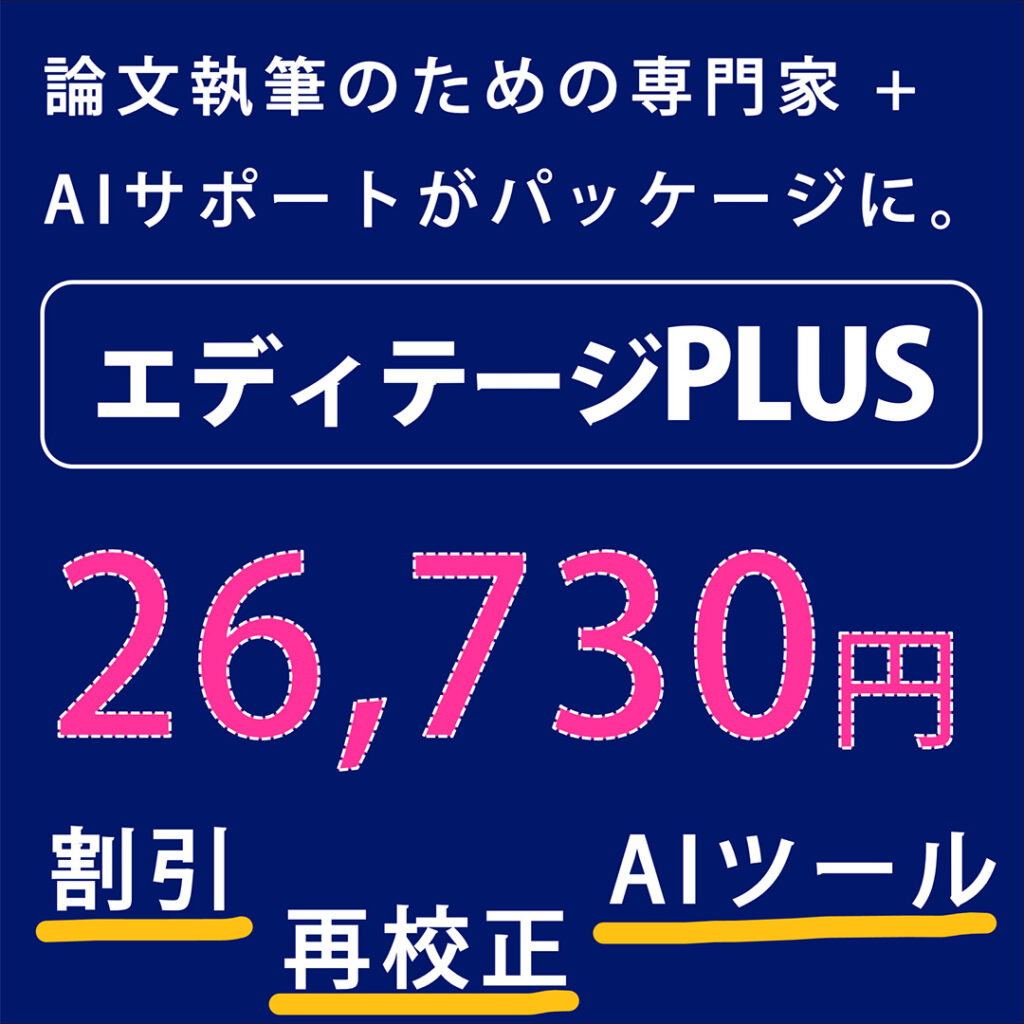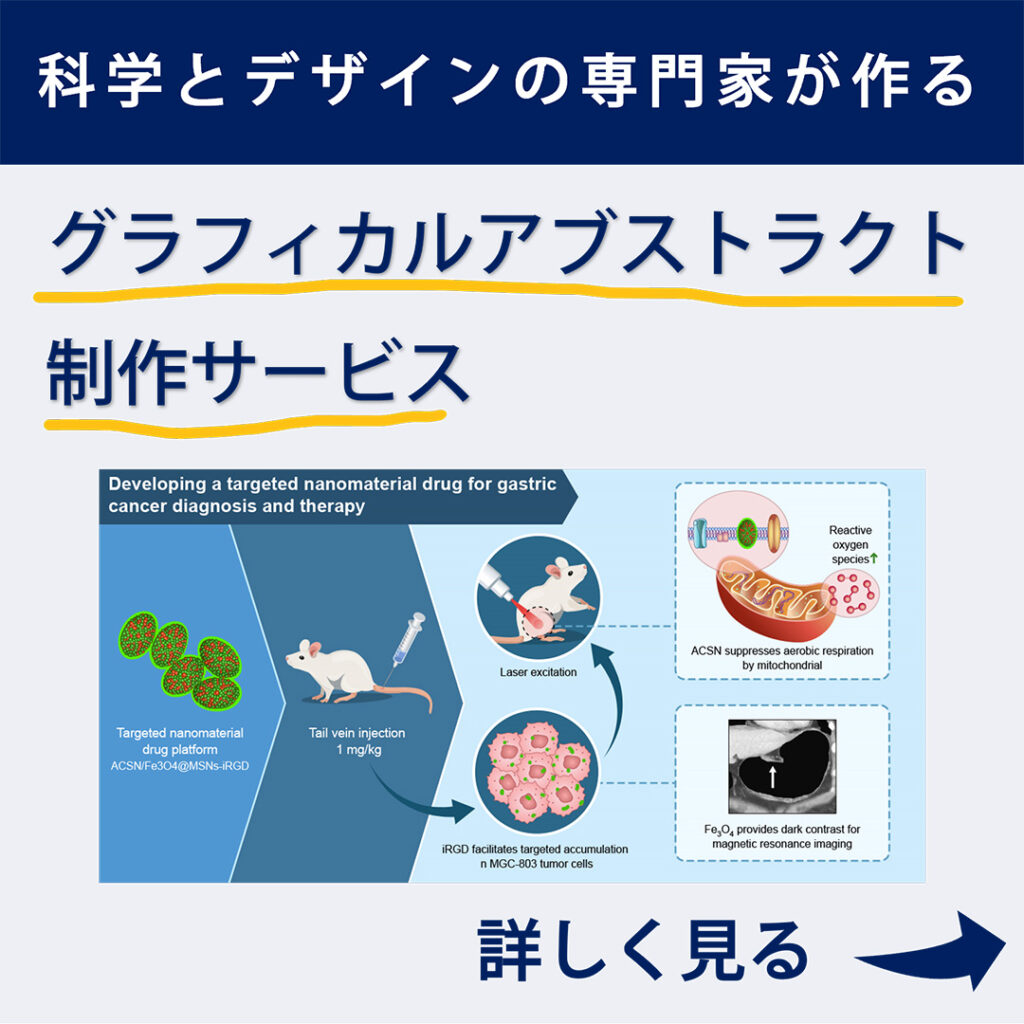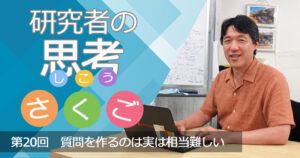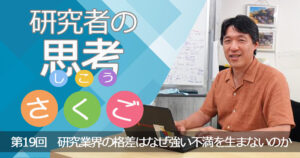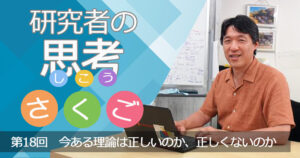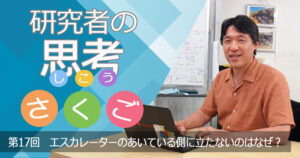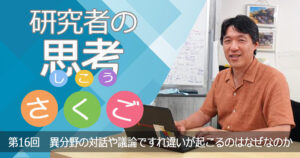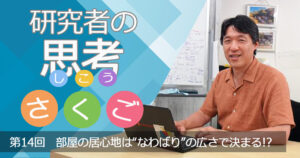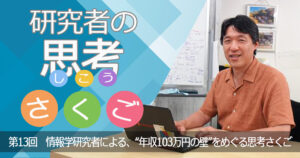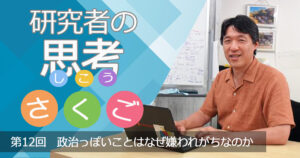大学の先生や執筆者が文章を書く際に、自分の考えや意見はどのように表現すべきなのでしょうか? 連載「研究者の思考さくご」第15回は、「人に嫌がられる物書きにならないためには」をテーマに、国立情報学研究所の宇野毅明(うの・たけあき)先生に情報学研究者ならでの視点で、ご自身の執筆時の経験もふまえながら考察していただきました。
いろいろ雑誌記事などを読むことがありますが、見ると大学の先生もけっこう記事を書かれています。専門的な立場があるので、他の人と視座や見立てが違い、考え方が新鮮だったりするので、読んでいて「いいなあ」と思います。一方で、楽しみに読んでいた連載が、だんだん回が進むにつれ、思想の押しつけのようなことを始めたり、特定個人(だいたいは悪いことをした人ですが)の悪口を始めたりすることがあります。「ああいうやり方はだめだ」、「こうでなければいけない」というものや、それが関係ない文脈でもどんどん出てくるようになり、大変残念な気持ちにさせられます。
自分がこの連載「研究者の思考さくご」を引き受けるときも、実はこの問題はけっこう気にしました。「書いているうちに変なことを言い出すんじゃないか」、「変なことを言っているのを自分では気がつかないかもしれない」、「大学の先生は変に”偉い認定”されているから、わけのわからないことを言っても見逃されているのではないか」などなど。どうしてそうなってしまうのだろう、どうやって防げばいいのだろうと、いろいろ考えました。
考えようとしても、自分がしたくないと思っていることをしてしまうときの心理状態や理由は想像するのが難しいものです。そこで、現在の自分の中の「人に思想を押しつけたい心」、「悪口を言いたい心」と話し合ってみることにしました。「書きものをしたい心」、「人に見せたい心」とも話し合い、状況の変化も考えてみることにしました。

考察1)ネタ切れになる
まず思いついたのは、「ネタ切れ」です。連載が始まるときは書きたいネタがたくさんありますが、連載が進むとだんだんと弾切れになってきます。人生何十年も経っていろいろとネタがたまっているところからスタートするのですから、この現象は当たり前で逃げようがありません。正確に言えば、「ネタが切れる」と言うより、「おもしろく書けることが減る」、ある程度つまらないものが増えるのだろうと思います。たとえば、時事ネタに対して解説記事を書くタイプの人は、時事ネタがある限りネタもおもしろさも変わらないはずです。しかし、その解説に毎回何らかのクリエイティビティ、新しさが必要となると、だんだんつまらなくなるでしょう。そのため、だんだん過激なことを言っておもしろくしたくなるのかな、と想像します。ある意味でサービス精神なのかもしれません。
考察2)読者からの反応を求めすぎる
次に思いついたのは自身の心の問題です。ものを書くときの原動力は、大部分は「誰かに何かを伝えたい」という気持ちだと思いますし、なぜ伝えたいかと言えば、それで「相手に何らかの影響を与えたい」からだろうと思います。あるいは「誰かの役に立ちたい、助けになりたい」という気持ちかもしれません。伝えたいものを書いた場合、読者から反応があれば「伝えられた」という実感を得られます。しかし、その反応は段々と少なくなるでしょうし、同じくらいの反応が続いたとしても、感覚がマヒして「伝えられた」という実感は段々と薄まりそうです。そうすると書く人は、より多くの反応が欲しくなり、だんだん強いことを言うようになり、だんだん過激になってくるのかと思います。
考察3)ネガティブな気持ちの表現
もう1つは自己表現、あるいは自分のネガティブな気持ちの開示でしょうか。「自分のことを表現する」心の裏には、「自分の気持ちをわかって欲しい」心があります。例えば、人に対して嫌な気持ちを持っていることや、何かが嫌だ、嫌いだ、苦しい、そういうことがわかってほしいとなったら、その表現が悪口になってしまうのかなと思います。あるいは、自分の立場や心の安全を守ろうとして、自分の規範を押しつけたくなり、その規範を破る人をネガティブな表現で攻撃したくなるのかな、とも思います。
結局、人に嫌がられるもの書きになってしまうのは、何かを欲張ってしまっているからなのではないでしょうか。「自分が書ける以上におもしろくしたい」、「この話とは関係ないけれど、相手がどういう人か知らないけど、自分の思想を伝えたい、納得させたい、自分の考えを理解させたい」。そういう欲張る気持ちをなくし、書こうとしているコンテンツをありのまま正直に書く。そう心に決めて、それ以上をしないことが防止策なのかと思います。

あとは、面白くしたければ話術を磨くこと、伝えたければ、納得させたければ、技術を磨くこと。他におもしろいことを書いている人がいたら、素直に学ぶこと。今の自分に満足しないで、あるいは欲望のまま書いてしまうほうに堕ちないように、自分の持っている技術をアップデートして、1レベル1レベル上げ、研究すること。新しいことを見て、知って、人の意見を聞いて、取り入れたり改良したりすること。そういうことが重要ではないかと思うのです。
考えてみると、なんだかごく普通の結論になってしまいましたが、ごく普通のことをするときに「なんでこれをしなければいけないんだろうか」、その理由がわかっているのといないのとでは大違いだと思います。そして、ごく普通のことを間断なく継続することはとても大変なことです。この連載の読者の皆さんも、筆者が変なことを書き始めたら連絡していただけますようお願いいたします。私は、「ちゃんと皆さんが通報してくれるかどうか、わざと変なことを書いてみようかな」という気持ちを我慢して、普通に書き続けようと思いますので。