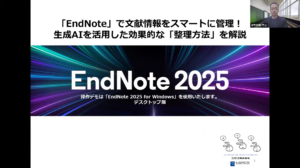研究活動において「英語での発信」は不可欠ですが、日本人研究者にとって、英語での論文執筆や国際共同研究のコミュニケーションは時間を取られる大きなハードルになりがちです。そんなときに頼りになるのが、学術英語に特化したAI 英語論文執筆支援ツール「Paperpal」です。
しかし、どれだけ便利なツールでも「実際にどのように役立つのか」が見えないと、使い始めにくいものです。基本的な機能は使えても、執筆の効率を高めるAI機能を使いこなせておらず、成果を実感しきれていないという声もよく聞きます。そこで、Paperpalの日本ユーザーの皆さんに「Paperpalのお気に入り機能を教えて」というアンケートを実施しました!
当ブログでは、実際のPaperpalユーザーの声をもとに「Paperpalのお気に入り機能と使い方、人気TOP5」をご紹介します。論文の書き始めから、翻訳や英文校正、パラフレーズ、引用管理など、研究現場でどんな場面に役立つのか、具体的な活用方法と成果を実際の研究者の声と共にお届けします。ぜひご自身の論文執筆をイメージしながらご覧ください。
なお、9月11日開催の無料ウェビナーでは、この記事でご紹介する各機能や活用方法をさらに具体的にご説明します。ぜひ下記のリンクからご参加ください。
Paperpalユーザーに聞いた!活用方法人気TOP5!
Paperpalには書き始める前の文献調査をサポートする機能から、執筆時の便利機能、最終チェック機能まで、様々な機能が搭載されています。その中から、今回のアンケート結果をもとに、実際のユーザーが活用している機能のコンビネーションを、人気順にご紹介します。
以下、それぞれの具体的なユースケースについてご紹介していきます。
🥇【1位】「単語数削減機能」 + 「英文校正機能」
どんなユーザーが、どんなシチュエーションで使っている?
- アブストラクトの単語数調整に悩む研究者の方や、ターゲットジャーナルを変更したことにより語数制限が変わった際に、PaperpalのAIに単語数調整を任せて内容に集中できる。
- 共著者と分担して書いている際の単語数調整にも便利。
使い方
STEP1: Paperpalで文書を開き、単語数を削減したい箇所をハイライト
STEP2:リライト機能の「単語数削減」を選択し、削減の程度を3つのレベルから選択
STEP3: 単語数が削減されたアウトプットを確認し、文書に挿入(AIの生成コンテンツは必ず確認し、調整を行うことでオリジナリティを保持しましょう!)
STEP4:英文校正機能で英語の正確性と読みやすさを磨く
ユーザーの声
「アブストラクトでどうしても減らせなかった単語数が、単語数削減機能を使う事で瞬時に調整でき、役立ちました」
「リライト機能で語数を削減した上で英文校正をすると、内容を損なわず投稿規定に沿った要約ができるので助かります」
「学会抄録など作成時にサクッと語数を減らすことが出来て助かる」
「英語論文執筆や国際学会での発表資料の校正の際に非常に役立っています!」
🥈【2位】「翻訳機能」 + 「学術英語に変換機能」
どんなユーザーが、どんなシチュエーションで使っている?
- 学内や学会で使用した日本語の発表原稿やデータから英語の論文を作成する場合や、論文を書く際にまずは日本語で書くという方は、Paperpal上で翻訳からスタート。英語に翻訳した後は、ワンクリックで学術英語表現に修正できて、自然な英語で効率良く書ける。
- 普段英語で書きなれている人も、どうしても英語で表現が思いつかない時には、日本語で書いてその場で翻訳機能を使う事で、スピードを落とすことなく書き進められ便利。
使い方
STEP1: Paperpalで文書を開き、翻訳したい文や段落をハイライト
STEP2: 翻訳機能を開き、ターゲット言語を選択して翻訳を実行
STEP3:翻訳された文章を確認し、文書に挿入(AIの生成コンテンツは必ず確認し、調整を行うことでオリジナリティを保持しましょう!)
STEP4:リライト機能の「学術英語に変換」を使って、学術的な表現へ変換
ユーザーの声
「ワードに書いた文章をそのままPaperpalで翻訳し、リライト機能で学術英語に書き換えることで、スピーディにまともな英文が仕上がるようになりました。論文執筆のスピードアップにおすすめです」
「日本語で書いてその場で翻訳できるのが便利。さらに言い換えチェックもワンクリックで採用・不採用を選べるので、ストレスなく作業が進められます」
「どうしてもうまく英語表現が思い浮かばないときには翻訳機能を使っています。学術英語への書き換えチェックはワンセンテンスごとに使っています」
🥉【3位】 「英文校正機能」 +「剽窃チェック機能」
どんなユーザーが、どんなシチュエーションで使っている?
- 英文校正機能は、共著者や指導員に見せる前、プロの英文校正者に原稿を依頼する前、大学の課題の提出前チェックなど、英語の間違いをなくし、表現を磨きたい時にすぐ使えて便利。
- ジャーナル投稿前や学位論文の提出前には、精度の高いPaperpalの剽窃チェックを使い、盗用の疑いがかかる箇所を特定し事前に修正が可能。
使い方
STEP1:Paperpalで原稿を開き、英文校正機能を使って、文法・語法・表現の精度を高める
STEP2:一貫性チェックも行い、時制や人称、専門用語が一貫して使われているかをチェック
STEP3:剽窃チェック機能を開き、完成した原稿をアップロード
STEP4:類似スコアと類似点をカテゴリーごとに確認して修正作業を行う
ユーザーの声
「英文の一貫性チェック機能が非常に便利です。さらに剽窃チェック機能は、なかなか自分では判断できない類似部分を客観的に検出してくれるので安心できます。」
「Paperpalは専門分野に即した文法・語法チェックをしてくれ、重複表現や盗用のリスクも検出できるので、投稿前の最終チェックにとても役立っています。」
「最近は投稿前に自己剽窃チェックが求められる場合もあるので使うようにしています。」
【4位】「執筆アシスト機能」 + 「学術英語に変換機能」
どんなユーザーが、どんなシチュエーションで使っている?
- 急に筆が止まってしまった時、ストーリーをうまくまとめられない時に、次の文章をAIに書いてもらったり、文章を段落に展開してもらったりすることで、アイディアを得ることができ、ライターズブロック(執筆の行き詰まり)を解消できます。そのあとは自分の言葉で伝えたい内容を書き、Paperpalに学術英語に変換してもらうことでさらに効率アップが可能。
- まだ論文の書き方に慣れておらず書き始めに苦労している若手研究者の方は、アウトラインをベースにした肉付け作業に執筆アシスト機能を使う事で、論文の書き方の学習にも。
使い方
STEP1:Paperpalで手元にあるアウトラインや途中まで書いた原稿を開き、内容を書き足したい箇所を選択
STEP2:執筆アシスト機能を開き、既存のプロンプト(例:「続きを書いて」「ここを展開して」「次の文章を書いて」)を使うか、プロンプトを入力してPaperpal AIで文章を生成
STEP3:生成された文章や段落を確認し、文書に挿入(AIの生成コンテンツは必ず確認し、調整を行うことでオリジナリティを保持しましょう!)
STEP4:執筆に勢いがついてきたら、表現は気にせずまずは書きたいことを書きだす
STEP5:リライト機能の「学術英語に変換」を使って学術表現に磨きをかける
ユーザーの声
「言葉に詰まったときに、良い文章を書くのに役立ちます。」
「考察の書き方に迷ったときに執筆アシスト機能(予測文章提案)で文章を提案してもらい、参考にできるのがとても助かっています」
「予測で執筆してもらったものをそのまま使うわけではないですが、論文の構成や流れのアイディアを参考にする事で効率的に執筆できていると感じます」
「執筆アシスト機能を使っていく事で、文章を考える際に、繋がりをより意識出来るようになった。」
【5位】「英文校正機能」 + 「リサーチ&引用機能」
どんなユーザーが、どんなシチュエーションで使っている?
- 英語論文の最終仕上げに、英文校正機能で間違いのない読みやすい文章に仕上げ、読み進めながら引用を挿入。
- 自分のPaperpalライブラリを構築しているユーザーは、裏付けが必要な文章や段落を選択してその場でライブラリから引用。引用するべき文献を文章ごと、段落ごとに検索する事もでき、初級者でも簡単。
使い方
STEP1:Paperpalで原稿を開き、英文校正機能を使って、文法・語法・表現の精度を高める
STEP2:引用が必要な個所を選択して、リサーチ&引用機能から「Cite text」を実行(またはライブラリから選んで引用)
STEP3:提示された文献をレビューして、適切なものを引用(次回以降また必要になる可能性が高い文献はライブラリに追加)
STEP4:必要があれば引用スタイルをアップデート
ユーザーの声
「なかなか自分で引用文献を探すのは一苦労ですが、これなら時短になり、その分浮いた時間を他の事に有効活用できる点がよかったです。」
「リサーチ&引用機能で引用文献を探すのが非常に楽になりました。調べきれなかった文献にもリーチできるので助かります。」
「ピンポイントで必要な文献を探すことが可能」
ワンポイントアドバイス!
Paperpalの引用機能を使って挿入した引用は、引用スタイルの変更が必要になった時にもワンクリックで自動更新され、とっても便利。さらに、Paperpalプライムユーザーになると、引用挿入時にリンクされた参考文献リストが自動で生成。
いかがでしたでしょうか?Paperpalの使い方のイメージは湧きましたか?
今回のランキングは、実際のPaperpalのユーザーアンケートの結果をもとにしています。研究者の皆さんのリアルな声が反映された事例なので、きっと共感できるポイントも多かったはずです。すでにPaperpalをご利用の方にも、まだ使った事がなかった機能をお試しいただくきっかけになれば嬉しいです。Paperpalにはこの他にも、「書き出しに便利なアウトライン生成機能」「投稿用カバーレターの作成」「PDFとチャット機能」「投稿前論文一括チェック機能」など、ここで紹介しきれなかった機能が揃っています。
「これ1つあれば論文執筆のすべての過程をカバーできる」「外注よりも安価でスピードも質も改善した」「教育現場での英文チェックにも有用」といった声も寄せられています。
研究者にとって、いかに効率良く質の良い研究論文を書き上げるかは大きな課題です。Paperpalは「言語の壁」を取り払い、研究者が本当に必要な機能を一括提供する事で、研究成果を世界に届けるための力強いサポーターになります。まだ使ったことがない方も、この機会にぜひ試してみてください。きっと論文執筆のスピードと質の両方を高める、新しい体験になるはずです。
さらに詳しく知りたい方へ📢
9月11日開催のウェビナーでは、今回ご紹介した機能や実際の使い方を、デモを交えながら解説します。ぜひこちらからお申し込みください。
Paperpalは、リアルタイムに言語と文法を修正するための提案を行い、著者がより良い文章をより速く書くことを支援するAIライティングアシスタントです。プロの学術編集者によって強化された何百万もの研究論文に基づいてトレーニングされており、機械的なスピードで人間の精度を提供します。