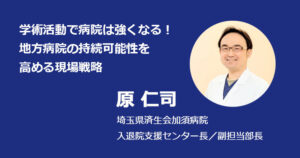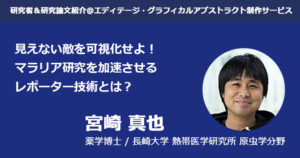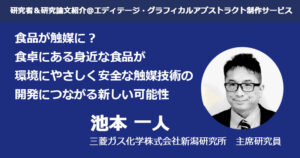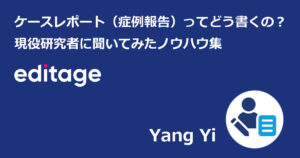エディテージ・グラント2024にて次点に入賞した柿沼 一雄さんに、入賞した喜びやご自身の研究について、グラントに応募して感じたことなどを語っていただきました。
柿沼 一雄さんプロフィール
Kazuo Kakinuma
2009年4月~2015年3月 東北大学医学部医学科
2020年4月~2024年3月 東北大学大学院医学系研究科 博士課程
2023年1~4月 KU Leuven Visiting Scholar
2024年4月~現在 東北大学大学院医学系研究科 助教
内科学会認定医、てんかん学会専門医、臨床神経心理士
学生時代はバンド活動に打ち込み、心理学・語学・言語学も趣味で独学。語学は、西語、独語、仏語、羅語、蘭語、中国語、韓国語、マレー語など、国際学会や論文査読で興味を持った言語を勉強している。また、国内外の伝承や信仰にも関心があり、各地の史跡や博物館を訪ねて、研究アイディアのインスピレーションをもらっている。

受賞した研究内容について
私たちの挑戦は、一言で言えば「脳のどの部分がどんな機能を担っているかを、患者さん一人一人について明らかにする」ということになります。これを脳外科領域では「脳機能マッピング」と呼びます。古典的なマッピング手法には「皮質電気刺激」がありますが、これを実施するためには手術で頭蓋骨を開ける必要があります。近年ではfMRIによる代替も進んでいますが、一人一人の個性を高精度に検出するには今一歩精度が足りない、というのが業界のコンセンサスです。私たち東北大学のチームでは、「マイクロカテーテルを使用して脳のターゲット領域だけに麻酔薬を注入する」という手法で、脳の個別領域が担う機能や、切除後の後遺障害の程度を推定することに成功しました。この新規の脳機能マッピング手法において、私は特に認知機能評価の部分に携わっています。今後は本手法の改善・発展だけでなく、定型化・普及にも力を入れていくつもりです。
エディテージ・グラント2024次点を受賞して
何よりもまず、多くの応募者の中から、この研究を選んでもらえたことが嬉しいです。
いつも私の論文には非常に多くの医師・研究者に共同研究者として携わってもらっています。この受賞は、こうした共同研究者のお力添えあってのものです。業界や組織といった既存の枠組みと一切関係のない「外の世界」で一定の評価をもらえたことはとても励みになります。「私の共同研究者はすごいんだぞ!」ということも世に示せたのではないかと思っています。大賞に届かなかったことは心残りですが、全体の応募倍率や他の受賞者の皆様を目にして、「こんなに凄い人がいっぱいいるのだから仕方がない」とも感じました。この錚々たる入賞者の末席に加えてもらえただけでも光栄です。
ご自身の研究について
私は東北大学病院の「高次脳機能障害科」という科で、脳の病気を診ています。ここには、「言葉がわからなくなった」「家の中で謎の人物が見えるようになった」「物忘れがひどくなったが、本人だけがそのことを認めない」などなど、様々な症状を持つ患者さんが訪れ、私たちはそれに対する検査や治療を行いながら、患者さんの協力を得て臨床研究を行っています。認知機能評価を診断に役立てるだけでなく、「患者さんの認知機能を維持・温存するためにはどうしたら良いか」といった観点で、研究と一体になった臨床を実践しています。脳神経外科・てんかん科など他の専門科とも臨床・研究の両面で協力しています。
もともと言語・文化・芸術といった方面にも興味があって、一時期は文系学部の進学も考えていました。しかし結果的には、そういった文化的現象を科学の目で解明したいと考えて、「ヒトの脳」を研究できる医学部に進学しました。そして臨床実習の中で、脳の部位と認知機能の関係を調べる「神経心理学」という学問に出会いました。当初は「脳と認知の関係を解明したい」という一心で門戸を叩きましたが、現在は「脳研究の知見は患者さんの役に立つ」という点にもやりがいを感じています。
「脳の科学的研究をベースにして、思考や行動といった文化的現象の一端を明らかにしたい」というのが私の一貫した目標です。そして、この謎を解き明かす「生き証人」として、現実の患者さんの存在は欠かせません。「文化的存在としての人間」には、実験室ではコントロールできない要素が多すぎるからです。過去の患者さんのおかげで私たちは脳を知ることができ、その脳研究の知見によって現在の患者さんには良い医療が提供され、そして患者さんの協力によってまた医学が進歩する。このループを持続的に回して、研究と臨床の共進化を発生させることが、実学たる医学の理想形だと思います。そして、私はその最前線で可能な限り脳の謎と格闘し続けたいと考えています。
エディテージ・グラントに応募した理由
普段からEditageの英文校正サービスをよく使っていたので、エディテージ・グラントについては告知メールやウェブサイトの掲示を見て知りました。学位を取得したばかりで自分の研究費がなく、若手向けの研究費助成を探していたところでした。
私の研究は臨床ベースなのでそれほど多額の研究費が必要なわけではありませんが、それでも昨今は競争的資金を取らないと学会参加や英文校正といった学術的活動に最低限必要の経費すら捻出できないのが現状です。学会発表や英語論文は学術成果のメルクマールでもありますから、それが出せなくなっては研究者として続きません。
グラントへの応募にあたり、苦労したことや工夫したこと
「自分の研究を資金提供者にアピールする文章」を書くこと自体が初めてだったので、レベル1からのスタートでした。まず申請書を書き始めるために「この研究を知ってもらうために先に伝えるべきことは何か」とか「今どこまで知られていて、私がその先を明らかにすると何が嬉しいか」ということを自分の中で形にしていきました。これは本当に骨が折れましたが、「自分の研究を自分のものにする」ために、とても価値ある作業だったと思います。後から科研費を取れたのも、この経験のおかげかなと思っています。
エディテージ・グラントに応募してみて感じたこと
全体的に見て、実績の少ない若手でも挑戦しやすいグラントだと思います。
応募時点で研究成果や外部資金がない人でも積極的に評価してくれますし、応募用のフォーマットはコテコテの研究計画書と比べてやわらかいので、研究計画書を書き慣れていない人でも不利になりにくいと思います。実際、私は今まで学振なども取っていなかったので、このエディテージ・グラントが初めてもらえた研究助成でした。ちなみに、エディテージ・グラントの後に科研費でスタートアップ研究と若手研究の計2件を採択してもらえました。
実績のない若手でも不利にならず応募できるレギュレーションで、最初の挑戦としてエディテージ・グラントに出して良かったと思っています。そして、応募こそハードルは低かったものの、セレモニーでお会いした皆さんは非常にハイレベルでした。他の受賞者の方々はみんなとても面白い研究をしていましたし、何より研究界の未来に対する熱意が溢れていました。おかげで私自身の研究のモチベーションもすごく高まりました。ちなみに、今回同じく入賞した大井由貴先生とは、その後に共著論文を執筆し、近々出版される見込みです。