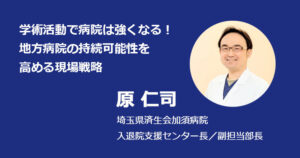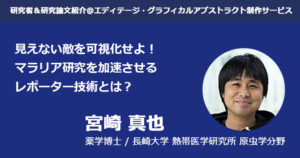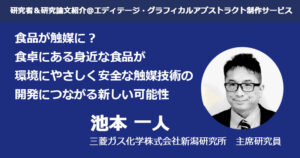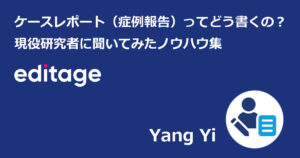エディテージ・グラント2024にて大賞に選ばれた岩永 薫さんに、大賞に選ばれた喜びやご自身の研究について、グラントに応募して感じたことなどを語っていただきました。
岩永 薫さんプロフィール
Kaoru Iwanaga
東京大学工学系研究科建築学専攻の西洋建築史研究室(加藤耕一研究室)の博士課程に在籍(日本学術振興会特別研究員DC1)。学部時代より同研究室に所属し、卒業論文では北欧建築史について、修士論文ではノルウェーの建築理論家クリスチャン・ノルベルグ=シュルツについての研究に取り組む。現在は、近代ノルウェー建築史に焦点を当て、市民が建物の維持管理に積極的に関わる文化がどのように根付いてきたのか歴史的に調査している。研究の傍ら、2度の育児休暇を取得しながら学業と育児の両立に努めており、博士課程での研究活動と並行して、伊東建築塾での執筆業務や京都芸術大学での非常勤講師も務めている。
休日は子供たちと散歩に出かけたり、公園で遊んだり、料理や掃除などの家事にも奮闘中。研究で得た建築への関心を日常生活にも活かし、DIYで収納を増やしたりと、より快適で自分好みの住環境になるよう模索している。趣味は読書。
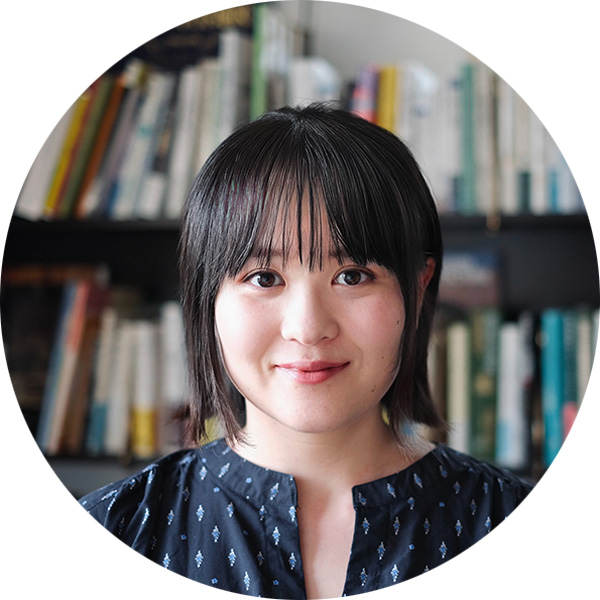
受賞した研究内容について
「近代ノルウェーにおける市民主体型建築ストックマネジメントの成立史」を研究しています。ノルウェーでは一般市民が自分の手で建物を建設・修繕する文化が根付いています。例えば、住民たちが集まって公的な建物の外壁を塗り直したり、小さな小屋だったら自力で建ててしまったりするのです。
日本では空き家が増加し、建物を「使い捨て」のように扱う傾向がある一方、ノルウェーではなぜ建物に自ら手を加え、長く大切に使う文化が根付いたのか。19世紀後半以降の歴史資料を調査し、この文化形成における社会背景や専門家の役割を明らかにしています。
この研究を通じて、日本の住環境問題への新たな視点を提供し、より持続可能な社会づくりに貢献したいと考えています。
エディテージ・グラント2024大賞を受賞して
このたびは、エディテージ・グラントの大賞をいただき、心より感謝申し上げます。北欧近代デザイン史の中でも比較的取り上げられることの少ないノルウェーの研究で受賞でき、その面白みや重要性を評価していただけたことに感無量ですし、大変励みになります。また、この受賞を通じて、建物を長期的な資産として大切にする文化が根付いたノルウェーの知恵を、日本の住環境づくりに活かせるよう、より一層研究に邁進し、しっかり完成させたいという思いも強くしました。
助成金は、主にノルウェーでの現地調査費に充てさせていただく予定です。実際に、2024年12月から2025年2月初旬に行った調査の費用として、その一部を利用いたしました。おかげさまで、西部の小さな村でインタビュー調査を行ったり、オスロのアーカイブ施設で貴重な資料収集をしたりすることができました。
ご自身の研究について
大学で建築学を専攻すると決めた際に、「実際にいろいろ見てみたい」という好奇心から友人と二人でバックパッカー旅行を決行しました。その旅の中でノルウェーを訪れた際にみた、スターヴ教会(木造教会)や、ナショナルツーリストルート沿いにある壮大な自然の中に佇む現代建築の姿がとても印象的で、ノルウェー建築に興味が湧いたのが、今研究している分野に興味を持ったきっかけです。
その後、ノルウェーを訪れて現地の方々のお宅に滞在する中で、日本では専門家に任せることが多い住宅の改修や修繕を自分たちで行ってしまう建築リテラシーの高さに驚かされました。現地では、未就学児のうちから刃物を扱い、大人も編み物や木工などそれぞれの得意な手仕事を日常的に行います。このように、「日常にものづくりが溢れ、その延長線上で、建築に手を入れて大切に使い続ける」というあり方が新鮮で素敵なものに感じ、その形成過程を学術的に研究してみたいと思うようになりました。
今後は、研究者としての社会的責任を果たしている、と実感できるような研究に取り組んでいきたいと考えています。ここで言う社会的責任とは、学術的な知見を広く社会に還元していくアウトリーチ活動を積極的に行うこと、そして私自身が大切だと思う価値観について深掘りしていくことで、より多くの人が幸せに生きていける社会にするための一助となることです。
また、近年、世界各国が様々な理由で内向きになる傾向がある中で、国際間の架け橋となるような研究の意義も強く感じています。異なる文化や社会背景を持つ国々の事例から、より普遍的な価値や物事の改善策を探っていきたいと思います。
エディテージ・グラントに応募した理由
エディテージ・グラントについて調べていく中で、業績だけでなく、研究への思いやポテンシャルを評価してくれるという点に強く惹かれました。以前の受賞者インタビューや審査委員の先生方のコメントを拝見し、研究者としての情熱や将来性も重視されていることを知ったのが応募の大きな動機です。
また、申請書の内容を見ると、研究の意義や展望について深く掘り下げる項目が多く、自分の研究意欲の原点を見つめ直す良い機会になると感じました。研究を進めるということに追われる中で、立ち止まって自分の研究の方向性を整理する貴重な時間となりました。
グラントへの応募にあたり、苦労したことや工夫したこと
指導教官だけでなく、色々な分野の先輩方にも目を通していただき、分野外の方にもわかりやすく的確な内容になっているか何度も推敲を重ねました。
エディテージ・グラントに応募してみて感じたこと
エディテージ・グラントへの応募から受賞まで、研究者として大きな成長を感じることができた貴重な経験でした。
応募の段階から、自分の研究の意義や今後の展望について改めて見つめ直す機会となりました。特に申請書を作成する過程で、日々の研究活動に追われる中では意識していなかった「なぜこの研究に取り組むのか」という原点や、「社会にどのように貢献できるのか」という視点を言語化することで、自分自身の研究への理解が深まりました。
また、授賞式も大変印象的でした。他の受賞者の方々のスピーチを聞いていると、研究への情熱が言葉を通して伝わってきて、同様の思いで研究に取り組む人間として胸にぐっとくるものがありました。また、自分のスピーチの際には、初めて会う大勢の方々の前で研究内容だけでなく、研究に込めた思いも語る機会をいただきました。頷きながら、しっかりと私の言葉に耳を傾けてくれているみなさんの表情がステージの上からよく見え、初めて、自分の研究が社会的インパクトを持ちうるという実感を得ました。
授賞式で紹介された言葉同様、今回の受賞でまさに研究者人生のスタートラインに立ったように感じ、今後の研究活動がより楽しみになりました。