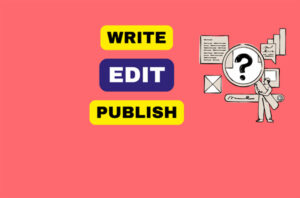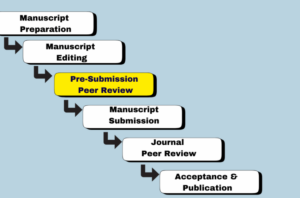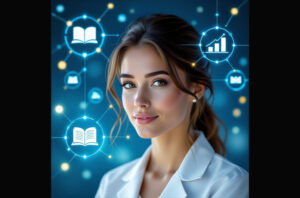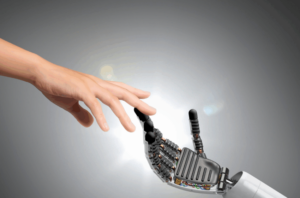研究者の中には、学生時代に突然指導教官からポスター発表をするように言われ、どう作ればいいのか分からず戸惑った、というような経験をしたことがある方も多いかと思います。特に毎年10月から11月にかけては 「ポスター発表シーズン」。このシリーズでは、これからポスター発表に挑む方のために、ポスター発表に関するすべてをシリーズを通してご紹介します。そしてこの第1回目の記事ではポスター発表の重要性についてご紹介します。
●筆者紹介
相澤有美
東京農業大学大学院博士課程修了(農芸化学専攻)。
専門分野は代謝学およびメタボロミクス。代謝経路解析や制御機構に関する研究、栄養学や分子生物学的研究に従事。
日本分子生物学会などに所属。

ネットで調べながらポスター発表についていざ手をつけ始めると、研究のまとめ方やデータの見せ方、限られたスペースで研究内容を伝える文章の工夫など、迷むことも多いです。
- どこから手をつければ良いのか
- 発表映えするデザインとは?
- すべてのデータを載せるべきか?
こうした悩みは、初めてポスターを作る学生や若手研究者だけではありません。久しぶりに学会に参加するベテラン研究者にも共通しています。しかし、「ポスター発表」という形式には、その苦労をするだけの 「魅力」があります。たった1枚の紙面で研究の本質を伝え、それを見た研究者と建設的な会話を生みだす——。研究にとって多くの学びの機会を提供してくれるポスター発表において、悩み試行錯誤するのは、実は自然なことなのです。
なぜ学会でポスター発表をするのか?
研究成果を発表する手段は、ポスター発表以外にも、論文発表、口頭発表、ポスター発表があり、目的によって使い分けが必要です。
論文発表は、研究成果を詳細なデータや解析とともに正式に「記録・公開する」手段であり、世界中の研究者が参照できるという大きな価値がありますが、出版までに時間がかかり、双方向の交流はほとんどありません。また、基本的に「完成した研究」のみを掲載するため、予備的な段階の成果や、方向性を模索している実験などは載せにくいという成約もあります。一方、口頭発表は「研究をストーリーとして短時間で伝える」手段で、理解しやすい反面、質疑応答の機会が限られ、聴衆に届くかはタイミングや運に左右されます。
これに対し、ポスター発表は研究者同士が直接対話できる場であり、時間の制約が少なく、相手の関心に応じて柔軟に議論を深められる点が最大の魅力です。
■ 論文・口頭発表との使い分け:まとめ
| 発表形式 | 目的 | 情報量 | 対話 | 適したタイミング |
| 論文 | 記録する | 全詳細 | × | 研究完成後 |
| 口頭発表 | 物語る | 要点+流れ | △(限定的) | 重要な成果を広く伝えたい |
| ポスター | 対話する | 核心のみ | ◎ | 予備的結果、ネットワーキング |
ポスター発表ならではの4つの強み
改めて整理すると、ポスター発表には以下のような独自の価値があります。
1. 双方向の対話が生まれる:口頭発表では、発表者が一方的に話し、聴衆は静かに聞くという構図が基本です。しかしポスター発表では、参加者の関心に応じて説明を変えたり、時には希望に応じて技術的な詳細について共有したりすることもできます。
2. 時間配分が自由:口頭発表は「15分」と決まっていますが、ポスター発表のコアタイムは通常1〜2時間。その間、何人もの研究者と話すことができます。さらに、口頭発表では、発表後に1、2人と立ち話をするのが限界ですが、ポスター発表ならコアタイムの間に10人、15人と接点を持てることも珍しくありません。
3. 予期せぬ出会いが生まれる:口頭発表は、専門ごとにセッションが分かれています。「分子生物学セッション」「神経科学セッション」といった具合です。しかし、ポスター会場では、様々な分野のポスターが混在しているため、自分とは異なる分野の人がこの手法は面白いと感じて新しい視点を提供してくれた。こうした「偶然の出会い」が生まれやすいのが、ポスター会場の魅力です。
4. 予備的な結果も発表できる:論文にするには時期尚早だけどフィードバックが欲しい。口頭発表で大々的に発表するほどではないけれど専門家の意見を聞いてみたい。そんな「まだ完成していない研究」を発表できるのも、ポスター発表の特徴です。「この方向で進めて大丈夫でしょうか?」や「別の解釈の可能性はありますか?」など、率直な質問を気軽に投げかけられる場でもあるのです。
ある研究者がそれぞれの形式で発表した例
ある研究者が、類似の研究成果を3つの方法で発表しました。参加者(読み手)からの反応という点において結果を比べてみると、次のような明確な違いがありました。
論文発表: 投稿から6ヶ月を経て、論文が掲載され、世界中の研究者が読めるようになりました。しかし、直接的なフィードバックはほとんど無く、数ヶ月後数件の引用がされましたが、読書や引用者と直接対話する機会は一度もありませんでした。
口頭発表: 200人の聴衆に対して15分の発表と5分の質疑応答を行いましたが、2人からの質問がありました。発表後、1人の研究者と立ち話で5分間議論しましたが、次のセッションが始まるため、途中で打ち切りとなりました。
ポスター発表: 2時間のコアタイムの間に、12人の研究者がポスターの前に立ち止まり、そのうち8人と深い議論ができました(各5〜15分)。名刺交換は6件。そのうち2件は、その後メールでのやりとりを経て、実際に共同研究に発展しました。
このように、ポスター発表は単なる研究発表の場ではなく、人脈を広げ、議論を深め、次の研究へとつなげるきっかけとなる大きな可能性を持っています。研究は発表して終わりではありません。他者との対話の中で新たな視点が生まれ、その視点が次のアイデアや共同研究を生み出します。
ポスター発表は研究内容を深める最良の手段の一つ
ポスター発表を経験したことのない方の中には、「なぜ教授はポスター発表をしろと言ったんだろう」と疑問に思う人もいるかと思います。ポスター発表は論文発表や、口頭発表では得られない、リアルな交流とフィードバックを得られる場であり、今後の研究を前進させ、また今後の研究に向けたアイデアや共同研究の機会を提供してくれる機会と言えます。
これからポスターを作る方は、「どう見せるか」だけでなく、「誰とどんな対話を生み出したいか」を意識してみてください。それが、発表の質を大きく変える第一歩になります。
次回は、「ポスターの役割」について、構成や情報整理のポイントを詳しく解説していきます。