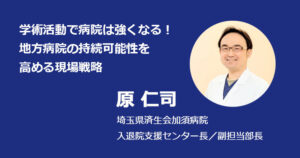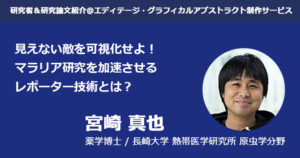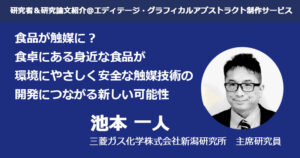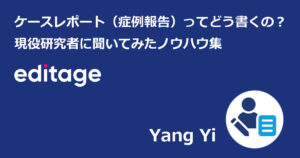エディテージ・グラント2024にて次点に入賞した村松 明穂さんに、入賞した喜びやご自身の研究について、グラントに応募して感じたことなどを語っていただきました。
村松 明穂さんプロフィール
Akiho Muramatsu
立命館大学文学部で心理学の基礎を学んだのち、京都大学大学院理学研究科に進学。日本学術振興会特別研究員、京都大学霊長類研究所・研究員、高等研究院・研究員を経て、秋田県立大学総合科学教育研究センター・助教。専門は動物心理学。これまでにデンショバト・チンパンジー・マカク(ニホンザルや近縁種のサルたち)・アミメキリンを研究対象としてきた。現在は主に動物園で飼育されている動物を対象とした研究に取り組んでいる。

受賞した研究内容について
従来は大学の研究施設で行われることの多かった動物心理学の研究ですが、最近では、動物園の来園者の前でオープンラボ型の研究として実施されることも増えてきました。動物園でオープンラボ型の研究を実施することにより、動物園で暮らす動物の動物福祉向上に貢献できる仕組みを作るとともに、来園者に対する環境教育としても活用することを目指しています。
エディテージ・グラント2024次点を受賞して
このたびは、このような機会をいただきありがとうございます。現所属である秋田県立大学に赴任して2年目での受賞だったため、新しい環境での新しい取り組みについて背中を押していただけたように感じ、大変励みになりました。また、前年にもエディテージ・グラント2023へ応募していたため、研究計画などをより良い内容にできたのではないかという点も嬉しく思っています。
ご自身の研究について
現在は、主に動物園での研究に取り組んでいます。秋田市大森山動物園と共同で、動物園で飼育されている動物がより幸せに暮らせる環境を、動物心理学の知見を活かして整えていく研究を行っています。また、長く生きるチンパンジーの生涯を通じた作業記憶能力の推移を調べる京都大学と共同での研究や、ニホンザルや近縁種のサルたちの社会性を比較する日本モンキーセンターと連携した研究にも取り組んでいます。さらに、大学生を対象とした環境教育プログラムの研究も開始しました。
高校生までの「生物への興味」と「ヒトの心理への興味」が、大学受験や入学後の学びを通じて、「動物心理学」として結びついたように思います。研究を通じてそれぞれの動物種の魅力を知ることができ、また、ヒトを含めた他の種との比較によって、私たちヒトがどのようにしてヒトになったのかを探ることもできる、「楽しい」分野だと感じています。
動物心理学や隣接領域・学問の知見を、研究を通じて、あるいは学生への教育を通じて地域に還元していけるよう、地域の施設・組織と協力しながら研究・教育に取り組んでいきたいと考えています。
エディテージ・グラントに応募した理由
一番の理由は、用途が限定されないという点です。多くの助成金プログラムは、応募時に研究課題・計画として提出した課題に対してのみ支出が認められており、さらにその中でも用途が限定される場合もあります。複数の研究課題を並行して進めている場合や、探索的な研究に取り組んでいる場合には、こうした制限により、研究費のやりくりが難しかったり、応募そのもののハードルが高くなったりするため、用途が限定されないエディテージ・グラントは大変魅力的でした。
エディテージ・グラントに応募してみて感じたこと
エディテージ・グラントは、エッセイとしてこれまでの研究やこれから取り組みたい研究などをまとめていくという形式が、他の助成金プログラムと異なるスタイルで新鮮でした。エディテージ・グラント2023にも応募したのですが、2023と2024との違い、2024の応募期間中に寄せられた質問への対応などに、様々な意見に耳を傾けてくださっていることが伺えました。研究者にとってのエディテージ・グラントの魅力のひとつは、応募理由としても回答したように、用途が限定されない点ではないかと思います。
応募の準備としてエッセイの課題に答える形で書き進めることにより、自身の研究のこれまでとこれからや、社会との繋がりについて、あらためて整理することが出来ました。また、お招きいただいたセレモニーでは、様々な専門分野の若手研究者や先輩研究者との交流を通じて、新しい視点から自身の専門分野や研究を捉え直すことが出来ました。